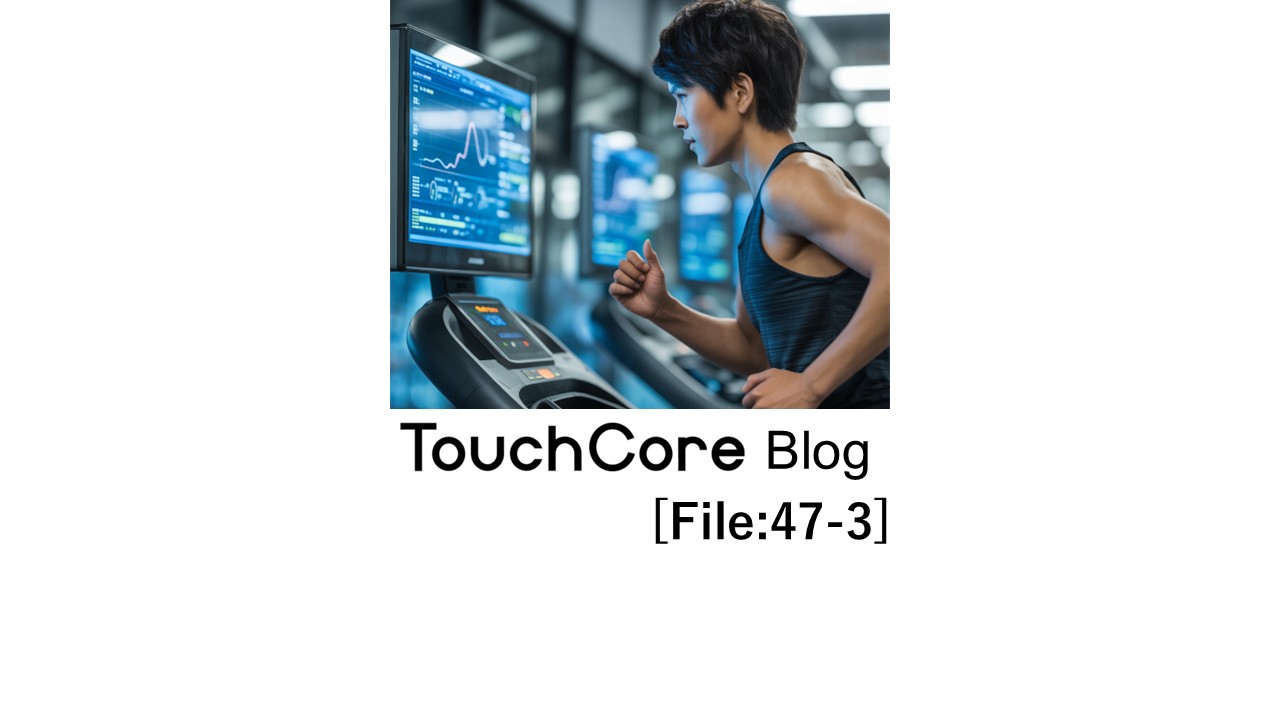
AIを経営に活かすには、業務を“方程式”として理解できなければなりません。
つまり、成果(Y)がどの要素(X₁, X₂, X₃…)の組み合わせで成り立っているかを、論理的に説明できることです。
ところが多くの日本企業では、業務が経験則と属人技で成り立っており、「なぜその手順なのか」「何が成果を左右しているのか」を説明できない。要素の関係式が曖昧なままAIを導入すれば、当然ながら分析結果も曖昧になります。
海外の先進企業では、この“方程式”の設計に長年取り組んできました。たとえば、工程・責任・評価指標を論理的に結び付け、業務の因果構造を図として共有できる状態が前提になっています。だからAIが「最適化」や「予測」を行っても、解釈と行動にズレが生じにくい。
一方、日本企業では、「現場が動いているから大丈夫」「数字が出ているから問題ない」という言葉がよく使われます。しかし、それは“結果”を見ているだけで、『構造(方程式)』を理解しているわけではありません。AIは「過去の結果」から規則を見つける道具ですが、構造を定義できなければ、その出力は“偶然の再現”に過ぎません。
経営とは、本来、成果の方程式をつくり直し続ける営みです。どの要素を変えると成果がどう変わるのかを仮説として設計し、検証する。この“方程式思考”こそが、AI時代のマネジメントの土台となります。
AIは、方程式を立てた後にこそ意味を持つ。逆に、方程式を持たない企業では、AIはノイズを増幅するだけです。
「業務を構造で捉える」ことは、もはや一部門のスキルではなく、経営の言語そのものなのです。
次の第4回(10/10)では、
・“方程式”を具体的に表現する技術=業務モデリング
・なぜ海外企業ではマネージャー自身が「モデルを描ける」のか
をテーマに掘り下げます。
合同会社タッチコア 小西一有
Leading sentence:AI導入の前に、マネジメントの四則演算をやり直そうー日本企業が失った「基礎体力」を取り戻す
第1回:AI導入は“上級問題”基礎体力なしに解けるはずがない
第2回:マネジメントの四則演算をやり直す