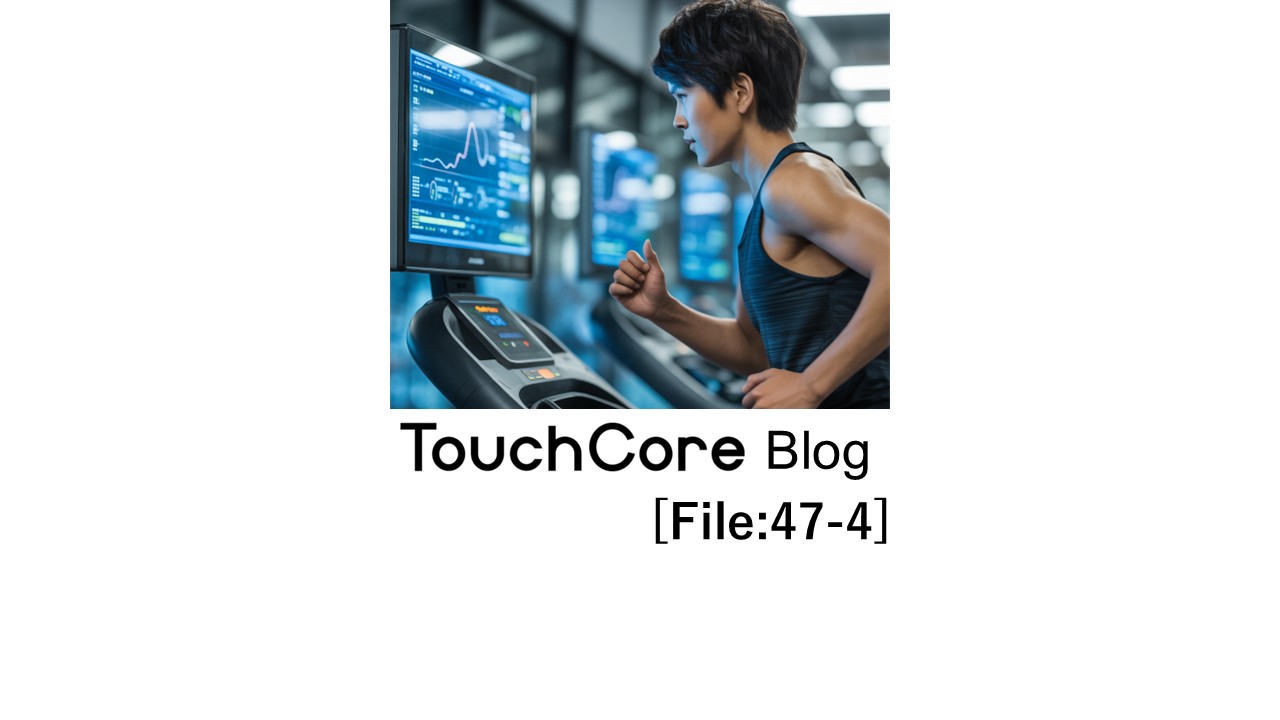
「業務モデリング」という言葉を聞くと、多くの人がBPMNや業務フロー図を思い浮かべます。しかし、本質は“図を描くこと”ではありません。業務を構造的に理解し、「なぜその流れで動くのか」を一次方程式のように説明できることが目的です。
たとえば、営業成果を「Y=a×提案件数+b×受注率」と捉えると、どの変数をどう改善すべきかが明確になります。これが“業務を方程式として理解する”ということ。その関係をチームで共有できるように可視化したものが、業務モデルです。
海外の先進企業では、このモデリングがマネージャーの基礎能力として定着しています。中間管理職が自ら業務構造を描き、目的・役割・データの流れを一貫して設計する。それが、AI導入時にも「どこにAIを適用すべきか」「どんなデータを学習させるべきか」を判断する土台になっています。
一方、日本企業では、「業務を回す」ことと「業務を設計する」ことが分断されています。現場は運用、経営企画は集計、IT部門はシステム——といった縦割り構造の中で、「全体を表す方程式」が誰にも見えないまま、AI導入が進められている。これではAIは、組織の中で分からないことを高速に処理する装置になってしまいます。
業務モデリングは、単なる文書化ではありません。組織の思考を構造化し、メンバー全員が「何を」「なぜ」「どうやって」行うのかを共有する言語です。AI時代に必要なのは、技術スキルではなく、業務をモデルとして語れるマネジメント力です。
一次方程式を解くように、業務の構造を整理する。
それができて初めて、AIは経営の“最適解”を導き出すパートナーになるのです。
次の第5回では、
・一次方程式(業務構造)を踏まえた「微積分=変化の分析」
・データを読めても“変化を設計できない”企業が陥る落とし穴
をテーマに掘り下げます。
合同会社タッチコア 小西一有
Leading sentence:AI導入の前に、マネジメントの四則演算をやり直そうー日本企業が失った「基礎体力」を取り戻す
第1回:AI導入は“上級問題”基礎体力なしに解けるはずがない
第2回:マネジメントの四則演算をやり直す
第3回:業務を“方程式”として捉えられるか?