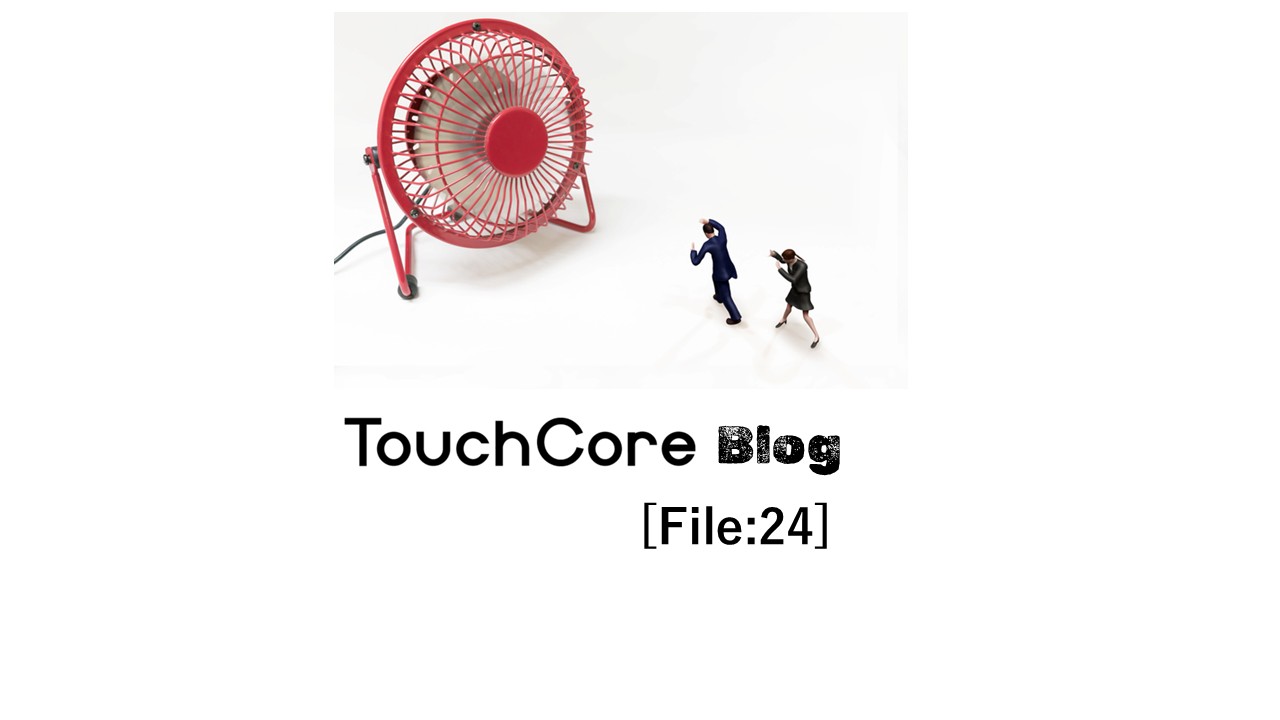
業務改革(Business Process Reengineering:BPR)。
BPRは海外では1990年代に必要性が叫ばれ、取り組みが始まっていました。
日本でも丁度その頃、バブル崩壊で注目されましたが生き残るためのコストカットが重要視されBPRへの取り組みは形骸化してしまいました。
やがて時が過ぎ、2010年頃から改めて日本でBPRに注目が集まりました。
しかし、この頃私はITリサ-チ・アドバイザリ-企業に勤めていましたが、日本企業のBPRへの取り組みは、主にERP(基幹システム)刷新に留まっていたように思います。
そしてまた時が過ぎ、数年前から業務改革について相談を受けることが多くなりました。
*ここからは「業務改革」と記述します
デジタルトランスフォーメーションの必要性が高まる中、当然のことだろうと思います。
ただ、いざ業務改革プロジェクトが動き始めると、多くの企業が同じ要因でプロジェクトが遅延または頓挫してしまうのです。
今回は、その要因である組織文化についてお話ししたいと思います。
■なぜ日本企業は業務改革に失敗するのか
■業務改革が失敗する組織文化要因
■業務改革推進で注目すべきポイント
■正しい見識を身に着けよう
■なぜ日本企業は業務改革に失敗するのか
業務改革とは、業務フロ-の見直しやシステム化(IT導入)ではなく、仕事の進め方(プロセス)を根本的に見直すことです。
言い換えれば、意思決定の仕組みといった「組織の価値観」にも影響を与えます。
多くの日本企業の業務改革が、この組織文化の変革で立ち往生し『業務改革プロジェクト』から『システム刷新プロジェクト』に置き換えてしまうのです。
それにも、失敗を許さないという日本の"文化"も影響していると思います。
まあそもそも、プロジェクトの『目的』が変わっているので、失敗はしていないと言えるのかもしれませんが。
■業務改革が失敗する組織文化要因
上手く業務の仕組みを変えたとしても、組織文化が変わらなければ当然定着もせず期待する成果は得られません。
(この期待する成果の設定についても問題があるのですが、それはまた別にお話ししたいと思います)
業務改革が失敗する組織文化というと、以下のようなものが挙げられます。
・変化を好まない(行動基準)
・堅牢な縦割り組織(部署毎の価値基準)
・脆弱なリ-ダ-シップ(意思伝達)
これらは相互に影響する要因なので、ひとつずつ解消すれば良いというものではないということがまた問題を重くしています。
-変化を好まない文化(行動基準)
日本人は「今までのやり方で問題なかった」「変えたからといって上手くいくのか」といった、いわゆる現状維持バイアスがとても強い。
結果、変革肯定の意見や行動はじわじわとかき消されていきます。
わかりやすいのは「多数決」。
この多数決というのは、いかにも『日本らしい』意思決定方法だと思います。
『日本らしい』には、2つの意味があります。
1つは、責任を皆で分担する的な意味合いを持たせてしまうこと。
失敗した時に「みんなで決めたじゃないか」という言い訳が通るとでも思っているのでしょうか。
多数決により「みんなで決め」て、責任の所在を明らかにしないのは日本文化といっても過言ではないでしょう。
もう1つの『日本らしい』の意味は、正しい見識、特に将来を見通すための見識を持つ者が排除されること。
「その見通しは正しいのか?」「確実にそうなると言えますか?」
将来の見通しを会議などで伝えると、こう詰問されることがよくあります。
ある仮説に基づいて将来予測をしていても、ネガティブな予測が含まれているとおおよそこうなります。
しかも、このネガティブな予測というのは、業績悪化などではなく「変化しなければならない」ことである場合が多いのです。
意思決定の場に参画する人々が「変化したくない」と考えているのでしょう。
そうして「時間も無いので決を取ります」と、ごく自然に却下されていくのです。
-堅牢な縦割り組織(部署毎の価値基準)
日本企業の多くは事業部制で運営されており、部署毎に価値基準や評価指標も異なります。
部分最適優先が常套であり、当然、他部署が関係する改革には消極的です。
これが全社横断の業務改革の障壁になろうことは、容易に想像できるでしょう。
それを解消すべく、業務改革プロジェクトでは多くの場合、各部署から担当が選出され「プロジェクトチ-ム」が設置されます。
そして、情報共有を促進するためにデジタルツ-ルが導入されることも多くあります。
(ただ、そのツ-ルの導入がプロジェクトの目的に置き換わってしまうことまであるから、要注意です)
さて、問題は人選にあります。
その部署の「価値基準を良く知っている」人材が選出されているのをよく見かけます。
例えば、ある程度責任のある人、部長級とか課長級とかです。
業務を変革するプロジェクトを推進する…ためのチ-ムであるのに、利益代表が集まる訳です。
プロジェクトリ-ダ-の「変化しよう」が、ごく自然に却下されても不思議ではありません。
-脆弱なリーダーシップ(意思伝達)
一番重い要因は、これだと言っても過言ではないかもしれません。
トップの問題意識を明らかにし、改革の意義を共有化させなければなりません。
例えば、プロジェクトリ-ダ-をアサインし、一度、中期経営方針とかで「メッセ-ジ」を発信し、後続はプロジェクト事務局にお任せ、プロジェクトチ-ムの人選もお任せという感じです。
また、プロジェクト進行中に利益問題が起こった場合に「今までの功績者」の意見を優遇するという対応もよく見られます。
リ-ダ-が、正しい見識を持ち、将来の見通しを持った人材を守らなければ、当然「変化しよう」は「何かやったことに」に変わっていくのです。
リ-ダ-は必要な人材を守ることは当然ながら、育成することにも熱心でなければならないと思います。
■業務改革推進で注目すべきポイント
今回は組織文化という阻害要因についてばかりお話ししてきましたので、業務改革推進にあたり、注目していただきたい点だけはお伝えしたいと思います。
まず、コミュニケ-ションコストに注目し、ビジネス目標を中心に業務設計を行うことです。
コミュニケ-ションコストというのは、組織内にある他所のチ-ムとの調整コストのことです。
機能が先ではなくコミュニケ-ションコストを極小化するための仕事の単位で考えるのです。
そして、ビジネス目標を中心に考える、とは、ビジネスの目的達成を第一に、ビジネスドメイン(業務領域単位)の理解を深め、システム設計や業務プロセスがどのように目的達成に貢献できるかを中心に据えるということです。
もっとこの業務改革推進の方法について詳しくお知りになりたい場合は、別途ご相談ください。
■正しい見識を身に着けよう
失敗とかその要因をお話ししていると「否定ばかりする」「上手く活かす方法を言え」といったご意見をいただくことがあります。
日本は今や世界競争力ランキングで世界67か国中の、38位と4年連続で過去最低順位を記録しています。
日本企業は抜本的改革を迫られているのではないでしょうか。
失敗の要因から目を逸らさず、その本質を正しく理解することは改革を進める上でとても重要です。
多くの皆さんに、正しい見識と問題意識を持っていただいて、一緒に将来のために議論していきたいと考えています。
[お勧め]無料体験:アドバイザリーサービス
合同会社タッチコア 代表 小西一有
