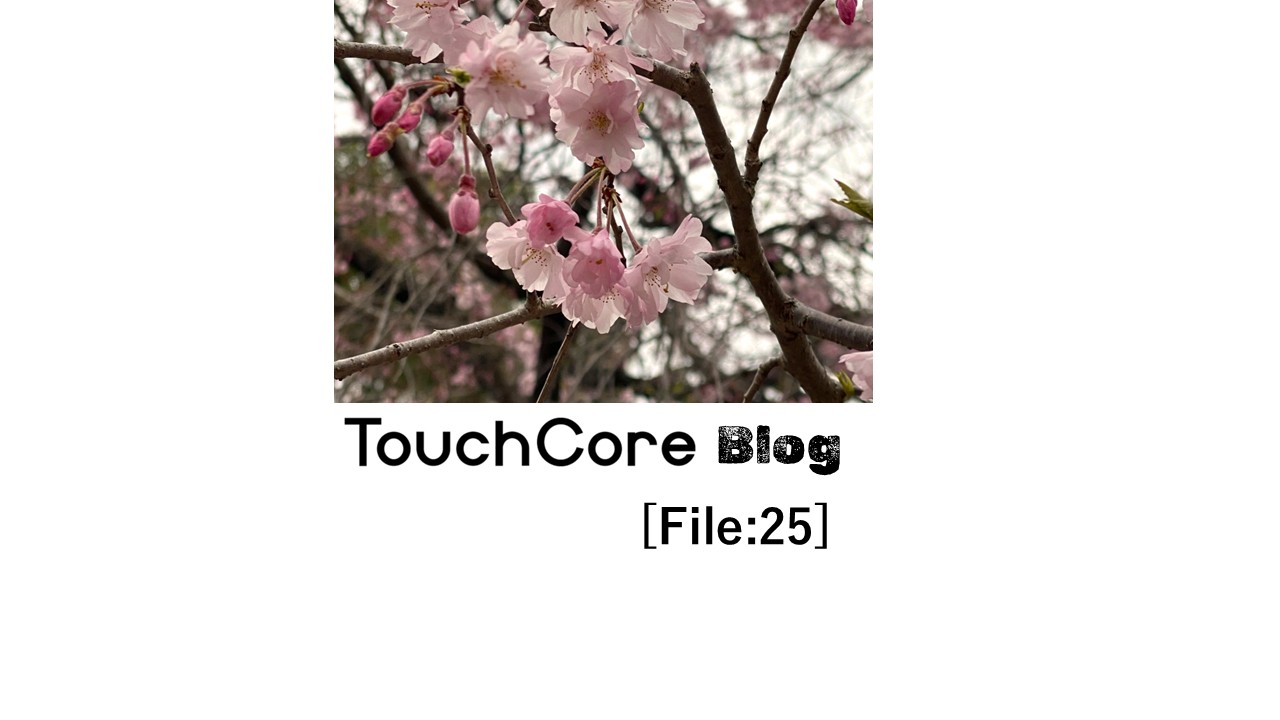
まずはお祝いを
ご昇進おめでとうございます。益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
今回の昇進は、皆さまのこれまでの努力と成果が認められた証です。
その一方で、新たな責任と期待が加わることも意味します。
今回は、新たな役職に就かれた皆さまが、どのようにマインドセットを整え、学び続けながら成長していくかの一助となるお話をしたいと思います。
■はじめにーなぜ昇進したのか?
■私のマネジメント経験ー最初からプロではなかった
■成長(学び)のモチベーション
■これからのマネジメントー重要な役割
■最後にー誰かではなく、あなた
■はじめに ― なぜ昇進したのか?
昇進の話(内示)は、どなたからお聞きになったでしょうか。
おそらく直属の上司から「4月からは『部(課)長』として頑張ってくれたまえ」と言われたのではないでしょうか。
その際には「有り難き幸せ」と、丁寧にお辞儀された方も多いかもしれません。
課長くらいならともかく、部長以上で「有り難き幸せ」と感じるだけでは心許ないものです。
多くの日本企業では年功序列的な仕組みが残っており、「そろそろ自分の番かな」と感じていたところに声がかかった、というケースも多いでしょう。
そのため「有り難き幸せ」と言わざるを得ない状況も理解できます。
しかし、ジョブ型雇用が機能している組織では、以下のようなやり取りが一般的です。
本部長:「4月から部長として活躍してくれたまえ」
新部長:「承知いたしました。ところで、新部長として何をいつまでに達成すべきでしょうか?
マネジメントの方向性について、変更すべき点があれば教えてください」
このように、ジョブ型の考え方では、役職に対して明確なミッションが存在し、それをどう果たしていくかが重視されます。
単なる年次の積み重ねでの昇進ではなく、自律性と実行力が求められるのです。
■私のマネジメント経験 ― はじめからプロではなかった
私が39歳で初めてライン部長になったのは、BtoC事業におけるカスタマーサポート部門でした。
そのとき、当時の上司からこう言われました。
「部のコストを可視化し、徹底的に削減してほしい」
「コスト削減に聖域はない。最短で成果を出すためなら、手法は問わない」
苦労も多かったですが、様々な施策を講じてこのミッションを達成することができました。
その結果、上司から次のような言葉をもらいました。
「有価証券報告書に君の功績が明記されている。実名は出せないが、ここまではっきりと『自分の仕事』と言えることは、ほとんどない。これは素晴らしいことだよ」
また同時に、業務品質の向上にも成功しており、当時の社長が、お客様からの感謝の手紙を嬉しそうに見せてくれたのを今でも覚えています。
この話は自慢のつもりではありません。
これからお話しする内容に深く関係するため、あえてご紹介しました。
「小西さんはコールセンターのプロだったんですよね?」
そう尋ねられることが、稀にあります。
ですが、私はそれまでシステム企画が中心で、どちらかというとプロジェクト推進を生業としていました。
15年以上、デリバリー中心の働き方をしてきたのです。
つまり、コールセンターの運営はまったくの門外漢でした。
しかし、直感でマネジメントしたわけではなく、徹底的に勉強しました。
社外に出て、多くを学んだのです。なぜなら、社内には有用な情報が少なく「それが常識ですから」と言われるような、都市伝説めいた話が多かったからです。
具体的には、業界誌で紹介されていた方に会いに行ったり、異業種混合のセンター長会議に参加したりしました。
同じような職位・立場の方との交流は特に役立ちました。
また、セミナーにも積極的に参加しました。
中にはベンダーの宣伝が目的の内容もありましたが、信頼できるコンサルタントによる講義は非常に有益でした。
マネジメントとは、最初からプロとして完璧である必要はありません。
重要なのは、学びながら実践し、改善を続けていくことです。
この姿勢こそが、信頼を勝ち取るマネジメントの本質ではないでしょうか。
■成長(学び)のモチベーション
学びとは、学校で「読んで」「書いて」「覚える」ことだけではありません。
新しい情報に触れ、自分で考え、人と議論することが、本質的な学びであると実感したのは、40代で東京理科大学大学院に通ってからでした。
大学院での学びを通して、「読んで」「書いて」「覚える」だけでは学びの本質に至れないことを痛感しました。
「社会人向けの夜間大学院コースでしょう?」と軽く見られることもありますが、私が通ったコースは、社会人経験を持つ方のみが対象で、平日夜間と土曜日に講義が実施され、必要単位は50単位以上。
フィールドワークも多く、非常に実践的でした。
昼間は外資系のリサーチ&アドバイザリー企業に勤務し、夜は大学院の講義を受け、さらに別の専門職大学院で教員としても講義を担当していました。いわば、三足の草鞋を履いていたわけです。
この経験を通じて、学びの大切さを実感したのです。
マネジメントにおいて、業務以外での学びは非常に重要です。
アカデミックな場での学び、他社の同職位の方々との交流、多様な業種・人・情報に触れることにより、高い視座を保つことができます。
例えば、ユニクロのセルフレジをご存じでしょうか。人手を介さず、商品数・内容をセンサーが読み取り、決済から袋詰めまで顧客自身が行います。こうした体験も、日常の中で学ぶきっかけになるのです。
また、異業種の店舗を訪問した際に見えるオペレーションの工夫や、従業員の応対姿勢、店舗レイアウトなどからも多くの学びを得ることができます。
五感をフルに活用して観察し、気づきを得ること。それも立派な成長の糧となります。
日常とは異なる体験や視点が、成長のモチベーションを高めてくれるのです。
■これからのマネジメント ― 重要な役割
日々の業務に追われ、余計なことを考える余裕がない方も多いでしょう。
しかし、これまで通りのやり方が通用する時代ではありません。
テクノロジーの進化だけでなく、戦争、円安、物価高騰、金利上昇など、外部環境は激変しています。
今までの延長線では間に合わず、「何をすべきか」「どう実行するか」を自ら創出する力が求められています。
こうした時代において、上級管理職に期待されているのは、過去の踏襲ではなく、自身のユニークなやり方で未来を切り拓くことです。
世の中や人々が今、何を求めているのかを感じ取る力。
社外からの情報を吟味し、自部門に活かしていく力。それこそが、現代におけるマネジメントの要諦です。
また、マネジメントは結果を出すだけではなく、組織に文化を築く役割も担っています。
チームに学びの文化を根付かせ、変化を恐れない姿勢を示すことで、組織はさらに強くなります。
これは、組織変革をリードする上で不可欠な視点です。
学び方を考えよう ― 学びは仕事
「何を言っているのかわからない」「そんなことは求められていない」と感じた方ほど、学びが必要です。
まず、現場業務を部下に任せられる体制を早期に整え、マネジメント層自身が「考える」ことに注力すべきです。
「時間がない」とよく言われますが、移動時間などの“ながら学習”では、受動的な情報しか得られません。
考え、対話し、深く掘り下げるための“集中した学び”が重要です。
おすすめは、学びの時間を業務の一部として位置づけることです。アウトプット前提での学びは、組織全体にも好影響を与えます。
また、社外に相談相手(雑談相手でも可)を持つことも有効です。
利害関係のある社内・ベンダーではなく、第三者的な視点を持つ相手が理想です。
弊社でも、中立的な立場でアドバイザリーを提供しており、「枠から出ることで視野が広がった」との声を多く頂いています。
マネジメントにとって、学ぶことは“仕事”そのものなのです。
時間を捻出し、意識的に投資する価値のある活動であると認識していただきたいと思います。
■最後に ― 誰かではなく、あなた
マネジメントを経験した私は、「読んで」「書いて」「覚える」だけの学びが、社会人にはあまり意味を持たないと痛感しました。
だからこそ、意味あるインプットを得て、深く思考し、質の高いアウトプットを行うことを推奨します。
コツコツやることが美徳とされる文化を変えていけるのは、あなた自身です。
「長いものに巻かれる」スタイルのマネジメントは、今後の企業において成果を生み出しません。
会社を変えるのは、大先輩ではなく、これからのあなたです。
新しい職位において、ぜひその力を発揮していただきたいと願っています。
そして、学びを止めず、変化を恐れず、自ら未来を切り開くマネジメント像をともに築いていきましょう。
[お勧め]無料体験:アドバイザリーサービス
合同会社タッチコア 代表 小西一有
