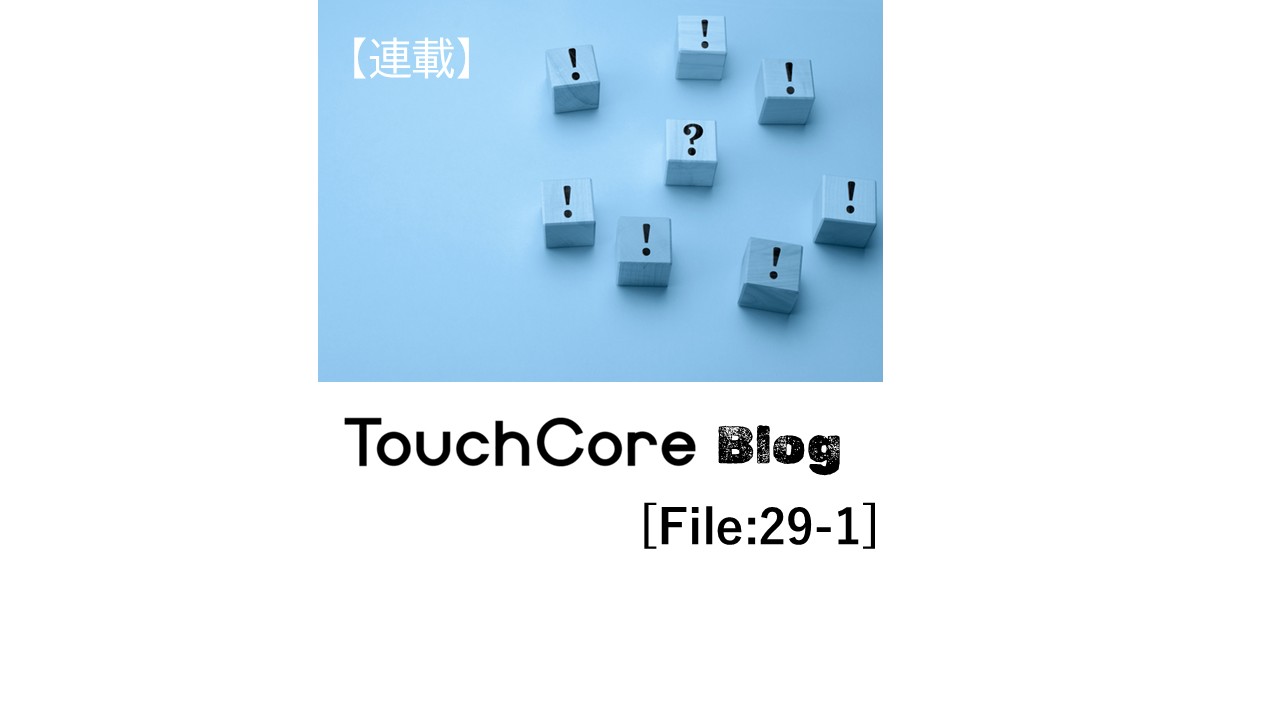
「業務改革=無駄取り」──このような認識が、いまだに多くの組織やコンサルタントの間で支配的です。特に、いわゆる「ECRS」(Eliminate:排除、Combine:結合、Rearrange:交換、Simplify:簡素化)というフレームワークに基づき、業務に潜むムダ・ムリ・ムラを取り除くことが改革だとする主張は、数十年にわたって受け入れられてきました。
もちろん、現場レベルでの無駄を省く取り組み自体は有意義です。しかし、私はこれを「業務改革の本質」と位置づけることには強く異を唱えたいと思います。なぜなら、実際に企業の中で業務を止めている本当の“無駄”は、そのような目に見えるムダ作業ではなく、むしろ「調整コスト」という見えない無駄にこそ潜んでいるからです。
調整コストとは何か?
調整コストとは、部門間や立場の異なる関係者同士が「すり合わせ」や「確認作業」「情報共有」「根回し」などを繰り返す中で発生する、目に見えない非効率のことを指します。
典型的な例を挙げましょう。ある企業で営業部門が「ある機能を追加したい」と社内開発部に依頼したとします。しかし、開発部は「その機能の要件定義が曖昧だ」「既存システムとの整合性が取れない」「他の案件の方が優先度が高い」といった理由でなかなか動かない。その結果、営業部門と開発部門の間で何度もミーティングが行われ、最終的には両部門の上長が関与する“調整会議”に発展する。このやりとりに1週間以上かかる──これは日常的に起きている光景です。
この1週間の中で実際に作業が進んだ時間は、おそらく1時間にも満たないでしょう。ほとんどの時間が「調整」という名の非生産的活動に費やされています。しかも、このやり取りの責任の所在は極めて曖昧であり、誰もこの時間の“コスト”を把握していないのです。
なぜ調整コストは見えないのか?
そもそも、私たちは業務を「構造」ではなく「担当者ベース」で捉える傾向があります。つまり、「この仕事は◯◯さんがやっている」「この業務は営業部の範囲」など、属人的かつ縦割りで業務を理解しているのです。そのため、業務の流れの中でどこにボトルネックがあるのか、どこで繰り返し調整が発生しているのかといった、構造的な視点での分析が困難になります。
また、日本企業においては「暗黙の了解」や「空気を読む」といった文化的背景もあり、業務の中に調整を前提とした“曖昧なグレーゾーン”が数多く存在します。これらは文書化されず、可視化されることもなく、改革の俎上に乗ることもありません。
これこそが、真の業務改革が進まない最大の原因であり、調整コストが“温存”され続けている理由なのです。
無駄取りだけでは改革にならない
ECRSを使った無駄取りのアプローチでは、例えば「この作業は削減できる」「この帳票は電子化すれば省力化できる」などの提案がなされます。しかし、それはあくまでも局所最適であり、組織全体のパフォーマンス向上には直結しません。
むしろ、業務の本質的な無駄とは、プロセスの分断や重複、責任の曖昧さ、情報の非対称性などに起因する調整の連鎖にあるのです。
ですから、表面的な効率化ではなく、業務全体を俯瞰し、構造的にどう再設計するかを考えることが、業務改革の出発点となるべきです。
次回、第2回では、調整コストの具体的な類型や発生パターン、そしてそれがいかにして業務の非効率と混乱を生んでいるかを事例を交えて解説します
合同会社タッチコア 代表 小西一有
