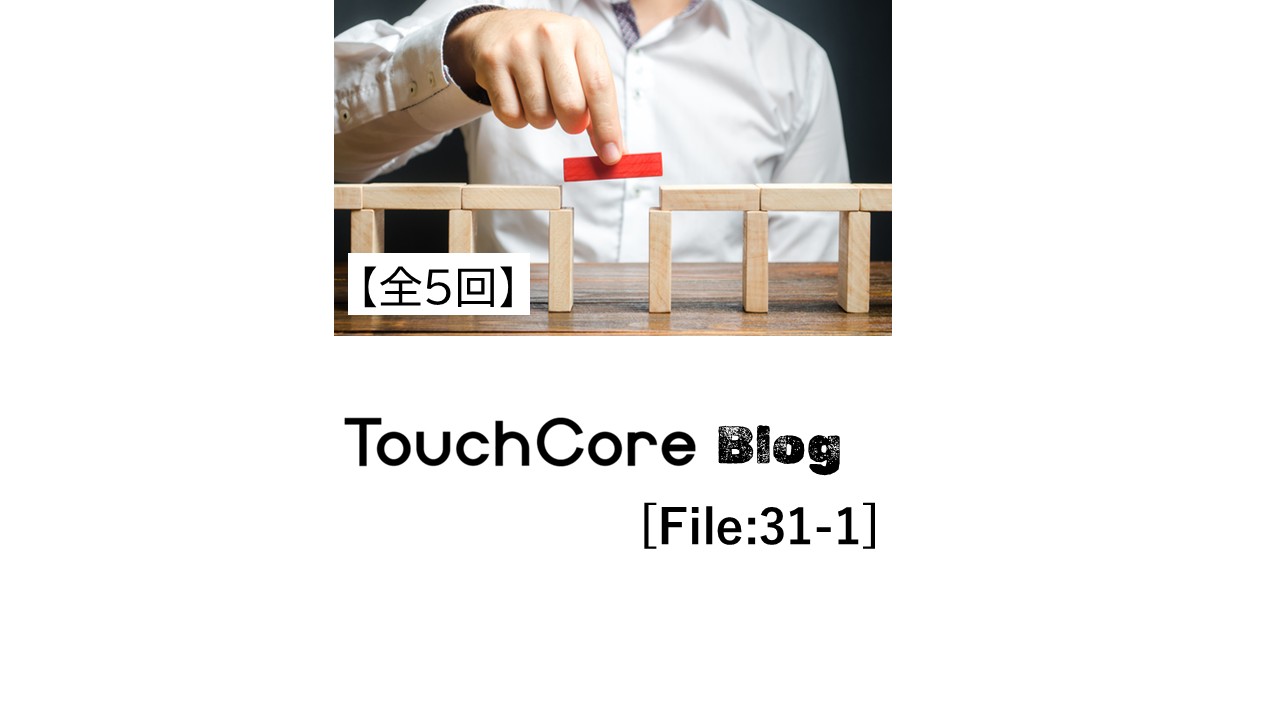
はじめに
エンタプライズ・アーキテクチャ(EA)や業務構造設計を組織に根づかせるには、誰が旗を振るべきか。
その最適な担い手は、経営層でも現場担当者でもなく、“中間管理職”です。
なぜなら、中間管理職こそが「戦略と現場」「経営の意図と日々の業務」の両方を理解し、実務として動かす立場にあるからです。
しかし、EAのような“構造的アプローチ”を推進するには、従来の「業務改善」や「タスク管理」とは違った新しい思考と振る舞いが求められます。
今回の連載では、中間管理職がEA導入を推進するために身につけるべき5つの振る舞いを、1回1つずつ紹介していきます。
第1回は、最も根幹にあるスキル、「構造で語る力」についてお話しします。
会議や打ち合わせは、なぜ通じ合えないのか?
業務改善やシステムの導入プロジェクトでは、よくこんな会話が交わされます。
•「ここのフローが煩雑で…」
•「あのデータ、いつも手入力なのですよね」
•「何度も同じことを別の部署でやっています」
こうした“現場の声”はとても貴重です。しかしそのままでは、「言語的な印象の共有」で終わってしまいがちです。
本当に必要なのは、それらの声を“構造としてとらえ直す”ことです。
言葉だけではなく、構造で語るとは?
「構造で語る」とは、次のような変換を指します:

通常の会話 構造での表現
「この業務、非効率なのです」 → 業務プロセスを図式化し、重複・分岐・手戻りを明示する
「このデータ、入力のたびに違うのですよ」 → データ構造(ER図など)を描き、更新主体と参照元を整理する
「各部門で似たことしているけど微妙に違って…」 → 業務ユースケースを比較して標準パターンと例外を定義する
つまり、言語情報を構造に変換し、“見える形”にすることが、アーキテクチャ思考の第一歩なのです。
モデルを描ける人が“議論の主導権”を握る
あなたの職場で、ホワイトボードに業務の流れを図で描き始める人がいたらどう感じるでしょうか?
多くの場合、その人が議論の主導権を取ります。
•全体像を見せる
•関係性を示す
•問題の位置を可視化する
これらは全て「構造的リーダーシップ」の発露です。EAを推進するには、“語る人”から“構造を描ける人”になる必要があるのです。
中間管理職に求められる「モデリング力」とは
とはいえ、複雑なUMLやBPMNを完璧に描ける必要はありません。
重要なのは、現場の業務をざっくり構造で整理する習慣を持つことです。
たとえば:
•「部門内の主要業務を3つのプロセスに分けてみる」
•「使っているデータ項目を整理し、どこで発生し、誰が使うかを図にしてみる」
•「顧客対応フローの変数(例外、分岐)を図で描いてみる」
このレベルのモデリングでも、十分に組織内の認識が揃い、再利用や共通化の議論が始められるのです。
「構造で話す」を職場に定着させるためのヒント
1.ホワイトボード/Miro/PowerPointなどを活用し、会話中に「描いてみる」文化をつくる
2.資料の冒頭に「プロセス図」「関係図」「業務フロー」を一枚載せてから詳細に入る
3.若手に「構造図の下描き」を任せて育成の場にする
4.「図があるとわかりやすいね」を口癖にして文化を育てる
これらは小さな一歩ですが、「構造で考える組織」への確実な前進になります
構造で語るとは、“抽象化”と“関係性”を描くことである
EAとは、全社的な業務・データ・システムの構造を、抽象化し、整理し、関係性を明示することです。
この思考を中間管理職が日常業務に持ち込むことができれば、プロジェクト全体が“構造駆動型”に変わっていきます。
「言っても伝わらない」
「誰かの頭の中だけに構造がある」
「同じ言葉を使っているのに、意味がズレている」
─そんな問題を解消する鍵は、「構造で語る力」にあるのです。
次回予告:「要望を聞く」から「問い直す」へ──構造的な問いかけをする力
第2回では、中間管理職が日々の業務やプロジェクトで実践できる「構造的な問い直し」の技術に迫ります。
「こうしてほしい」「困っている」と言われたとき、EAを志す管理職がとるべき反応とは?
課題の背後にある“構造のゆがみ”を見抜くためのフレームと実践例をご紹介します。
合同会社タッチコア 代表 小西一有
