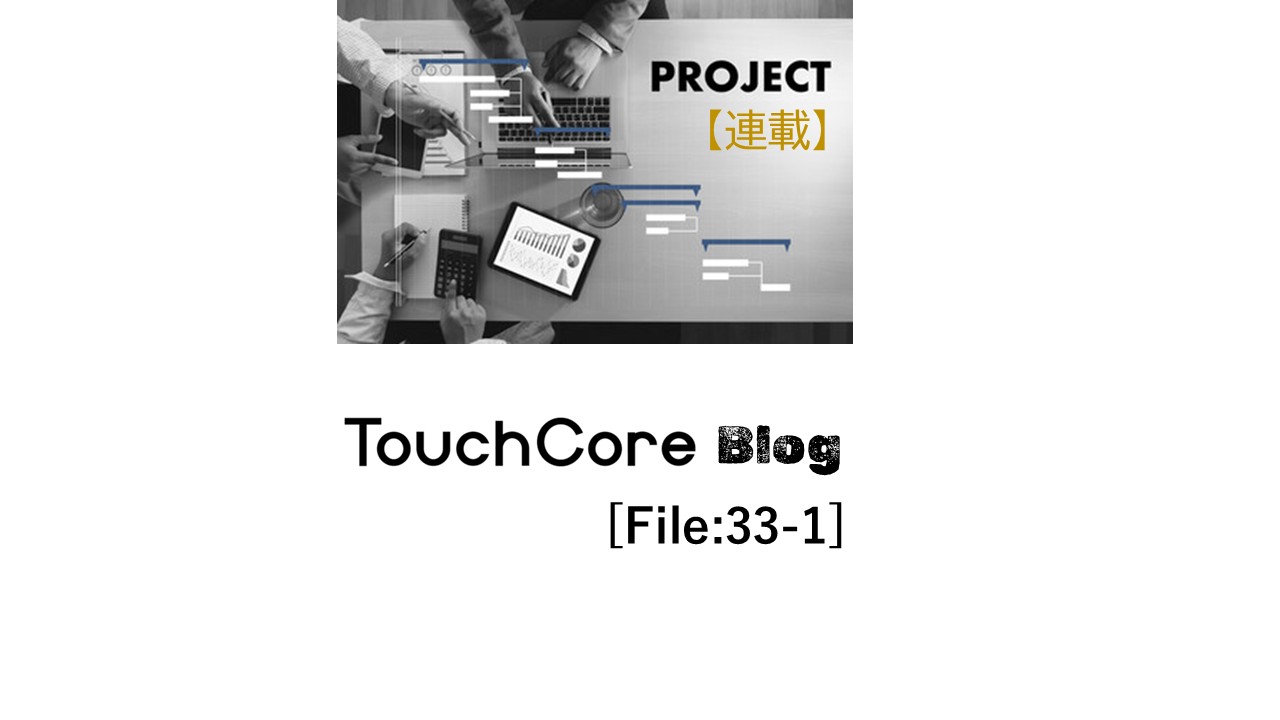
はじめに
PMOって結局、誰かがやらないといけない雑用を引き受ける係ですよね」
大規模プロジェクトに関わる現場から、そんな声を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。多くの企業や自治体でPMO(Project Management Office)の設置が進められる一方で、その真の価値が認識されず、結果的に「調整役」「資料作成係」「会議招集担当」など、雑務中心の役割に押し込められてしまっている現実があります。
しかし、本来のPMOの役割とは、プロジェクトの成功に向けて「構造を見直し」「思考を促進し」「人と組織を動かす」ための知的支援組織です。なぜ、そのような本来の意図が失われ、「雑務係」になってしまうのか。その背景には、組織構造の問題だけでなく、心理的な要因も大きく関わっています。
なぜPMOは「雑務係」になるのか?
原因の一つは、「誰もやりたがらないが、誰かがやらなければならない業務」の存在です。会議の日程調整、議事録の作成、進捗報告のとりまとめ…。これらは確かに重要ではあるが、誰がやっても差が出にくく、評価されにくい業務です。そして、プロジェクトメンバーが本業に集中したいあまり、これらの業務は自然とPMOに押し付けられます。
PMO側も「役に立たねば」という気持ちから、その期待に応えようと奔走してしまう。こうして「何でも屋」や「便利屋」としての立場が定着してしまうのです。
心理的メカニズム:PMOが「思考を止める存在」になる危険性
もう一つの本質的な問題は、現場の人々がPMOに対して抱く「依存」と「距離感」です。
•「PMOが考えてくれるから、自分たちは決めない」
•PMOが取りまとめてくれるから、個別対応で済まそう」
このように、PMOが本来支援すべき「意思決定者」や「実行主体」が思考を放棄してしまう構造が生まれます。これはPMOにとって非常に危険な状態であり、プロジェクト全体の知的活動が停滞する兆候です。
一方、PMO側も、こうした依存関係を「頼られている」と誤認し、自らの役割を「調整力」「実務処理能力」として自己肯定してしまうことがあります。心理的には一見安定した関係に見えますが、これは「相互の思考停止」を伴う非常に脆い状態です。
「支援」と「代行」の違いを明確にする
本来、PMOは「思考の支援」を行うべきであり、「判断の代行」や「実務の請負」をする組織ではありません。PMOがするべきことは、プロジェクトの複雑性や曖昧性を構造化し、関係者が主体的に考え、判断できるように整えることです。
そのためには、以下のような意識転換が必要です:
•PMOは「やってあげる」のではなく「考えさせる」支援をする
•関係者にとっての「問い」を明確にする
•状況の見える化・共通言語化を通じて、思考の出発点を共有する
PMOが「役に立つ」ことの危うさ
「PMOは役に立つ」と言われると、多くのPMO担当者はうれしく感じるかもしれません。しかし、その「役に立つ」が「雑務を引き受けてくれる」ことを意味しているのであれば、危険信号です。
PMOが真に果たすべき役割は、「見えない障害を取り除き」「沈黙しているリスクを可視化し」「曖昧な論点を明確にする」ことです。それは往々にして、目に見えにくく、成果が評価されにくい仕事です。だからこそ、組織の中で誤解されやすく、孤立しやすいのです。
合同会社タッチコア 代表 小西一有
