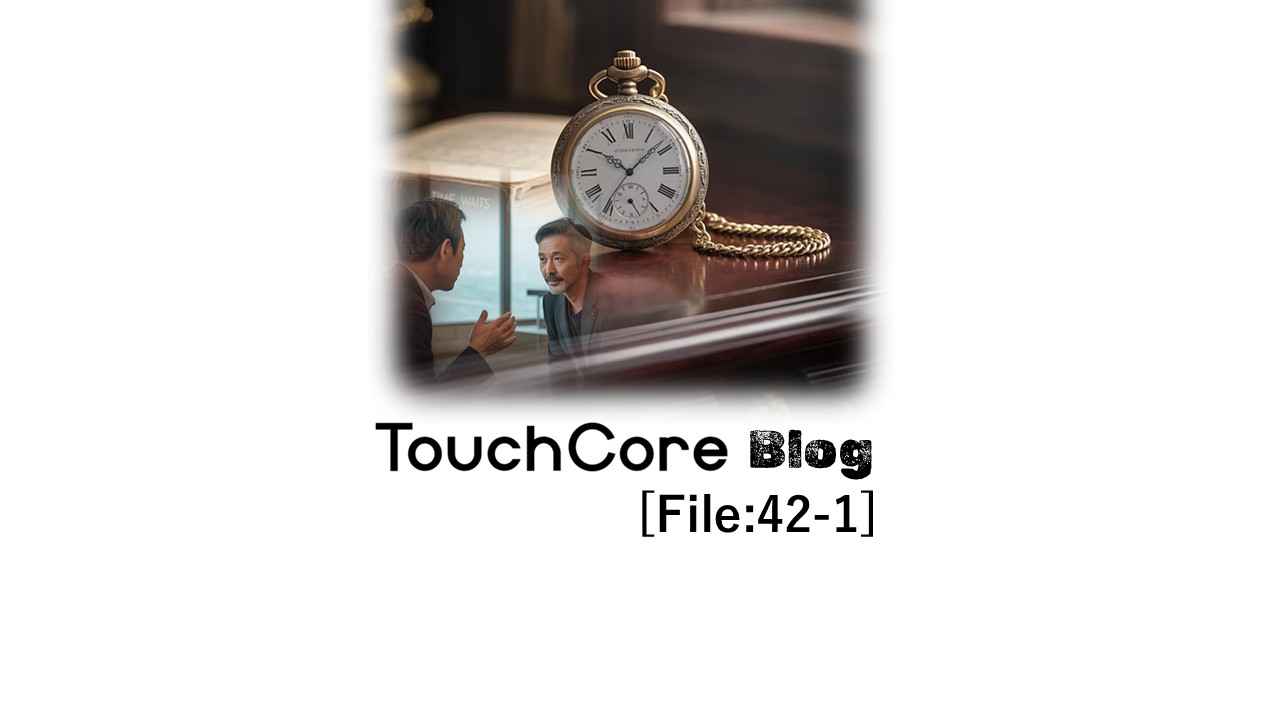
「コンサルティング」という言葉を耳にしたとき、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。
多くの方が連想するのは、外部の専門家が企業に乗り込み、膨大なヒアリングと資料調査を行い、厚い報告書を提出する姿ではないでしょうか。日本のIT業界でよく見られるのは、
「自動化ニーズ調査」→「要件定義」→「開発受託」→「開発実行」→「リリース」→完了、
という“丸投げ型”の流れです。企業は外部にすべてを委ね、ベンダーは請負業務として回収する。これが長らく「コンサルティング」の名で語られてきました。
確かに、このスタイルは短期的な成果物を生みます。しかしその一方で、経営の本質的な課題は解決されないままです。報告書は机の中に眠り、システムは形骸化し、経営者や幹部が自ら考える機会を奪われてしまう―そんな光景を私たちは何度も見てきました。
アドバイザリーは「答えを渡す」存在ではない
当社が提供するのは、こうした従来型コンサルティングとは本質的に異なるものです。私たちは自らを「経営に関する戦略的アドバイザリーサービス提供会社」と位置づけています。
アドバイザリーの役割は、外部が「答え」を持ち込むことではありません。経営者や幹部が自ら考え、意思決定を下せるように「視座」と「問い」を提供することです。経営の現場で本当に必要とされるのは、報告書でもシステムでもなく、「判断の軸」なのです。
「伴走」でも「代行」でもなく
よく「伴走支援」という言葉も使われます。確かに、経営者に寄り添い現場を手助けするスタイルは安心感をもたらします。しかしその多くは、外部が常に隣にいることを前提にしています。これでは結局、依存から抜け出すことができません。
アドバイザリーは、伴走でも代行でもありません。短期的に支援した後、社内に「考える力」を残し、外部がいなくても自走できる状態を目指します。つまり「外部がいなくなった瞬間から価値が始まる」存在なのです。
経営の本質は「意思の実装」
企業とは、経営者が社員を率いて顧客に価値を提供する存在です。そのために「人・物・金」といった経営資源を動かし、戦略を実行します。しかし、経営資源をどう活かすかは「意思」にかかっています。
残念ながら日本では、ITやDXと聞くと「自動化」「効率化」に短絡的につなげてしまう傾向があります。ITは本来「経営の意志を現場に落とし込むための仕組み」なのに、目先の効率化に矮小化されてしまうのです。
アドバイザリーが注力するのは、この「経営の意志をどう実装するか」という部分です。技術や仕組みをどう選択するかよりも前に、「何を意志として持ち」「どう現場に伝えるか」という経営の根幹を扱います。
アドバイザリーの本質的な価値
つまりアドバイザリーの価値は、以下のように整理できます。
・依存を生まない:成果物や外部常駐に頼らせず、社内に考える力を残す。
・意思決定を支える:報告書ではなく、問いや視座を提供する。
・経営の意志を実装する:効率化ではなく、戦略を現場に落とし込む仕組みを考える。
私たちは「知識を売る」のではなく、「考える文化を定着させる」ために存在しています。
皆さんへ
あなたの会社が本当に必要としているのは、報告書やシステム開発でしょうか。
それとも、経営の意思を形にするための「考える力」でしょうか。
もし後者に価値を見出すなら、アドバイザリーという選択肢があることを知っていただきたいのです。
次回(第2回)は、「経営における情報の特性とアドバイザーの役割」と題し、「情報」をどう扱うかが経営を左右する理由を掘り下げます。
合同会社タッチコア 小西一有