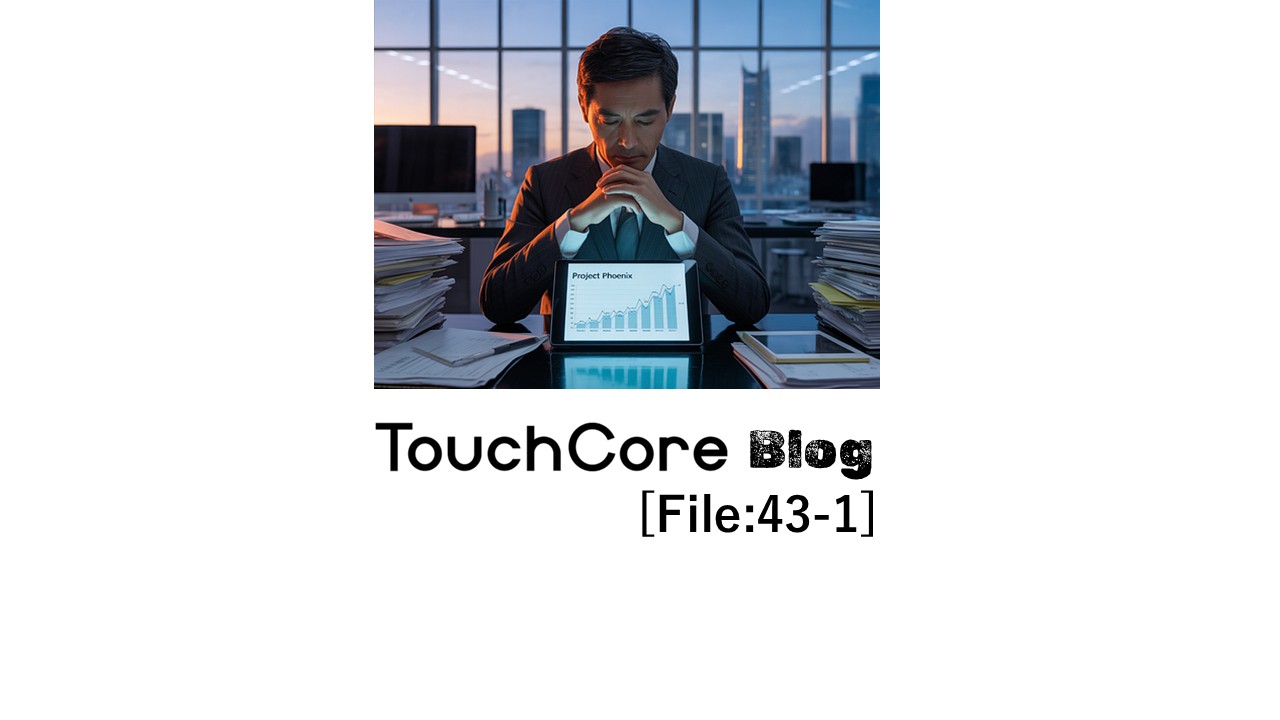
経営者の多くは「情報が不足しているから判断できない」と考えがちです。けれど、実際の現場では正反対のことが起きています。むしろ「情報は山のようにあるのに、行動に移せない」という現象の方が圧倒的に多いのです。
例えば、DXの必要性が叫ばれてから既に数年が経ちました。政府レポートや各種調査が「旧来システムに依存すれば競争力が落ちる」と警鐘を鳴らしています。それにもかかわらず、多くの経営者はまだ「分かっているけど、うちはまだ大丈夫」と判断を先送りにしています。ここには、合理性では説明できない心理の壁が存在します。
情報過多の時代に「正しさ」は埋もれる
第一に、私たちは既に「情報過多」の時代に生きています。経営者が受け取るレポート、セミナー、コンサル提案、社内資料、等々、すべてが「正しさ」を主張しています。しかし、その“正しさ”が多すぎるために、かえって何を信じればよいのかが分からなくなっているのです。
つまり、経営者にとって必要なのは「正しい情報」ではなく「納得できる物語」です。情報が正確かどうかよりも、自社の歴史や価値観と矛盾せず、自分自身が腹落ちできるストーリーであるかどうかが、行動を左右するのです。
感情と習慣が理性を上回る
次に重要なのは、意思決定は必ずしも理性によって行われるわけではないということです。心理学的に言えば、人間は“認知バイアス”に強く支配されています。
例えば、「今のやり方で問題なく回っているのだから、わざわざリスクを冒す必要はない」という現状維持バイアス。あるいは「競合もまだ動いていないのだから、自分だけ先走るのは危険だ」という同調バイアス。
これらの感情や習慣が、頭で分かっている“正しい情報”を簡単に打ち消してしまいます。経営者も人間である以上、理屈よりも「居心地のよさ」や「安心感」を優先してしまうのです。
行動に移せない経営者の典型的な口癖
現場でよく聞くのが次のような言葉です。
・「分かってはいるのだけどね」
・「今はタイミングじゃない」
・「他社の動向を見てからでいいだろう」
これらは、正しい情報を受け取っていながら行動できないことの裏返しです。情報の正しさは認めている。しかし、“行動に移す理由”としては弱すぎる。だから自分を納得させる言い訳をつくり、結局は先送りにしてしまうのです。
情報の「正しさ」よりも「使い方」
ここで強調したいのは、「正しい情報」を持つことが意思決定のゴールではないということです。正しい情報をどう使うか、どう自社に取り込むか、その“変換作業”が伴わなければ、ただの知識の断片に終わってしまいます。
行動できる経営者は、情報を単なる“材料”と捉え、それを自分なりのシナリオに落とし込みます。そして、完璧な確信がなくとも「小さく試す」ことから始めるのです。
まとめ
経営者が正しい情報を前にしても行動できないのは、情報が不足しているからではなく、「正しさを自分の物語に変換できていない」からです。次回は、この行動を妨げる最大の要因の一つ―「過去の成功体験という呪縛」について掘り下げていきます。
合同会社タッチコア 小西一有