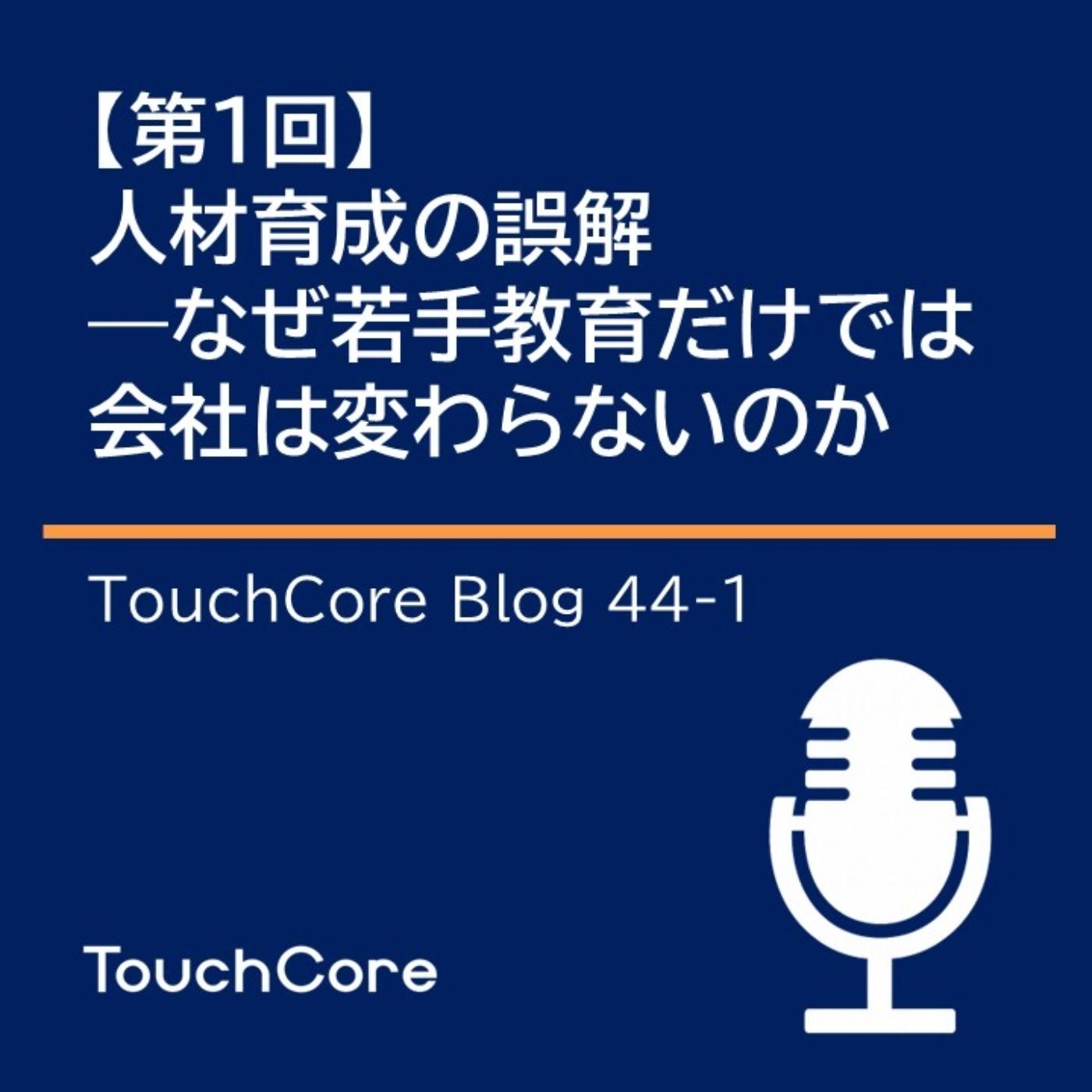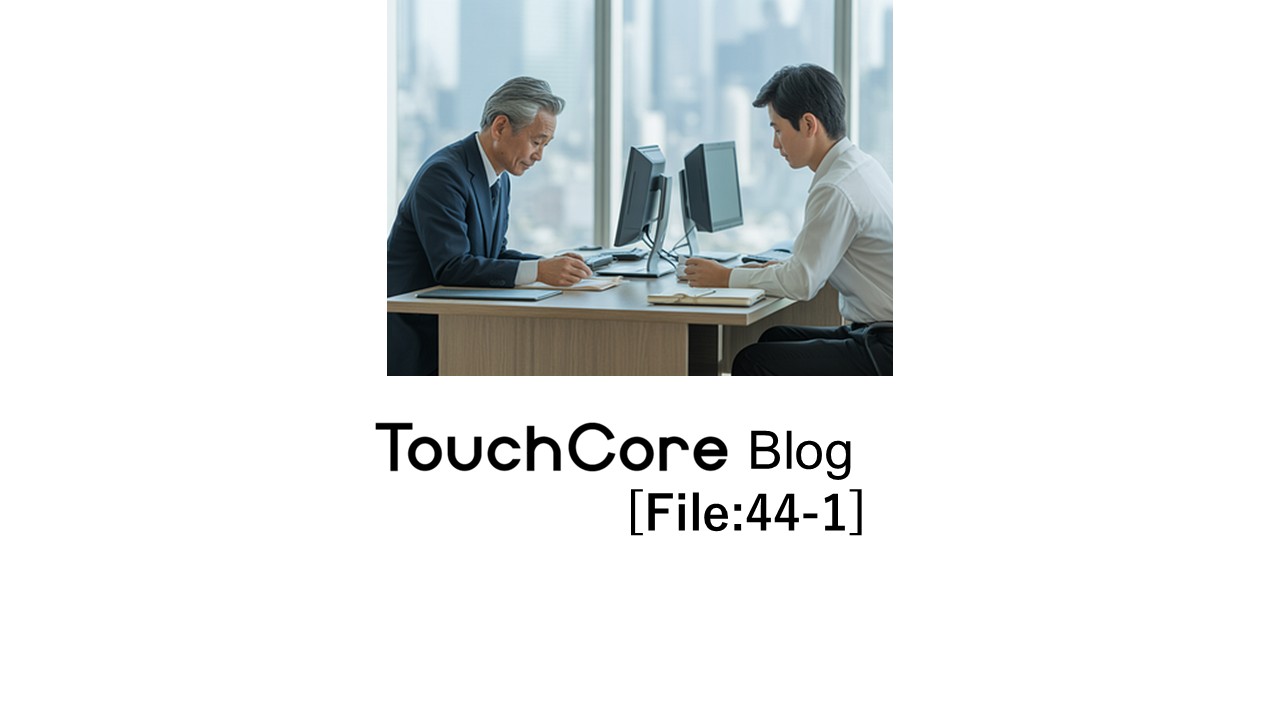
人材育成という言葉を耳にしたとき、多くの経営者や人事担当者が最初に思い浮かべるのは「若手研修」ではないでしょうか。新入社員研修や、入社3年目研修、あるいはリーダー候補者向けの短期的なトレーニング。
もちろん、若手社員を鍛えること自体に意味がないとは言いません。しかし、私は強い危機感を持っています。「若手教育=人材育成」という思い込みが、会社の変革を阻んでいるのではないかと。
若手が育っても、会社が変わらない理由
考えてみれば当たり前の話です。若手がいくら研修でスキルを身につけても、最終的に会社を動かすのは幹部層と経営層です。意思決定を担う人たちが学ばずに、これまでのやり方に固執している限り、若手がどれだけ優秀であっても、その力を活かせる場は与えられません。
私は長年、数多くの企業の現場を見てきました。その中で痛感するのは、変革を阻んでいるのは若手の力不足ではなく、むしろ幹部層の「学ばなさ」です。
「自分はもう十分に経験を積んでいるから学ぶ必要はない」と考えてしまう。あるいは「教育は若い人のためのものだ」と思い込んでしまう。そうした姿勢が、組織の硬直化を招いています。
教育の中心を誰に置くべきか
経営者や幹部層は、教育というと「部下
のために用意するもの」と考えがちです。ですが、本当に会社を変えたいならば、教育の中心はまず自分たち自身に置くべきです。
ここで一つ問いを投げかけたいと思います。
―あなたの会社の幹部職員は、過去5年間で何を学び直してきたでしょうか?
業務知識の更新や資格取得だけでなく、「経営の潮流」「組織を率いる力」「デジタル時代の戦略の立て方」について、本気で学ぶ場を持った幹部はどれくらいいるでしょうか。
もし答えに窮するならば、その会社の未来は危ういかもしれません。なぜなら、幹部が学ばない組織は、必ず遅れていくからです。
人材育成を「若手」に押し付ける危うさ
若手教育に力を入れる企業は少なくありません。しかし、それが「幹部層が学ばないことの言い訳」になってはいないでしょうか。
「若い人たちに新しい知識を学ばせて会社を変えてもらおう」と期待する。けれども実際には、若手は決裁権もなければ権限も持ちません。組織の上に立つ幹部が学び、方向性を示さなければ、若手の知識やスキルは机上の空論に終わってしまうのです。
変革は「下から」ではなく、「上から」始める必要があります。トップがまず学び、幹部がそれに続く。その姿を若手が見て、初めて学びの連鎖が組織に根付くのです。
経営者自身が学び直すことの意味
私はこれまで、数多く
の経営者や幹部層と議論を重ねてきました。その中で気づいたのは、「学ぶ経営者は、社員教育を戦略の一部として考えている」ということです。
単なる人
事施策としての教育ではなく、「未来の成長を実現するために、どのような人材が必要か」という視点を持っている。だからこそ、まず自分が学ぶ。自ら変わる。その姿勢が社員に伝わり、組織全体を変えていきます。
逆に言えば、経営者自身が学ばない会社では、教育はコストの一部にしか見えません。社員に研修を受けさせても、そこから何も生まれないのは当然です。幹部が学び直す気がない会社に、未来はありません。
変革の第一歩は「常識を疑う」ことから
人材育成は若手のた
めにある――この常識をまず疑ってみてください。
会社を変えたいなら、幹部や経営層が学ばなければならない。
教育を「自分には関係ないもの」と思う限り、組織の成長は望めません。
私は、幹部や経営者自身の学び直しこそが最大のレバレッジになると確信しています。そして、その学びを支え、伴走することが私の役割です。
次回は、「幹部教育こそ最大のレバレッジ――組織を動かす層を鍛える」をテーマに、さらに具体的に掘り下げていきたいと思います。
幹部教育や経営
者の学び直しに関心のある方は、ぜひコメントやメッセージでご意見をお聞かせください。
私が伴走者となり、貴社の人材育成戦略を共に考えるお手伝いをいたします。
合同会社タッチコア 小西一有