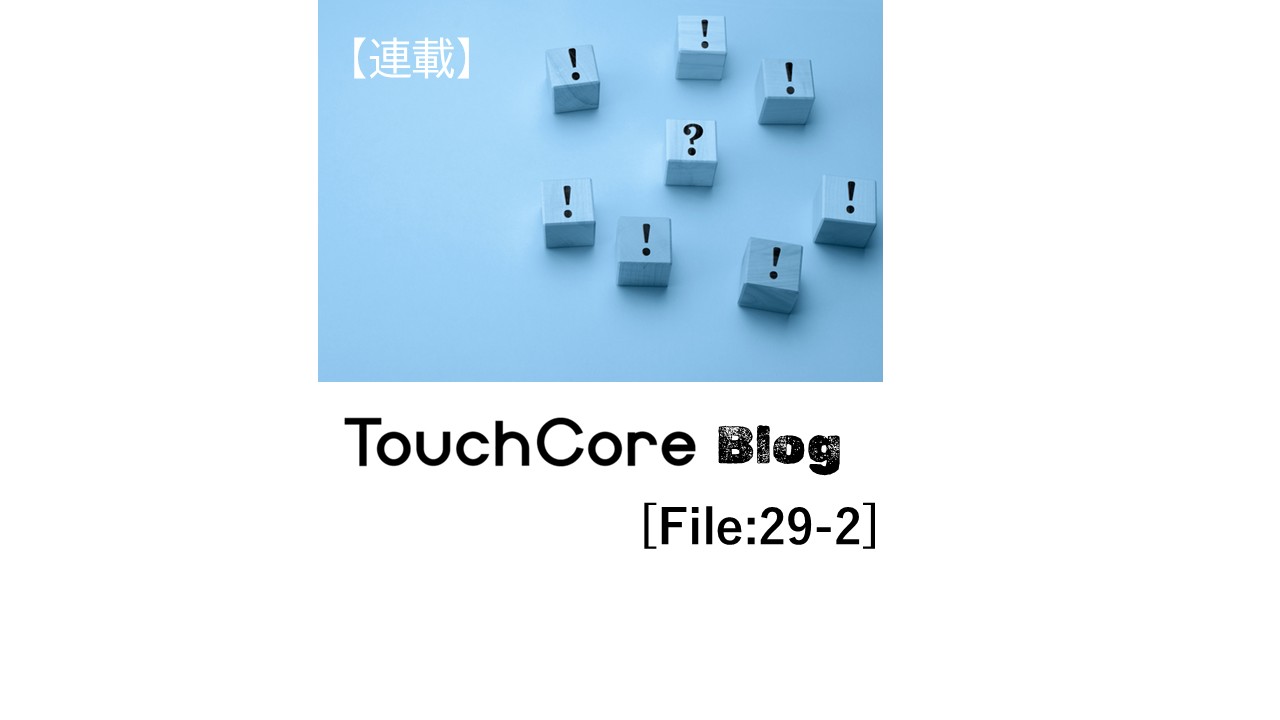
第1回で、「業務改革とは“無駄取り”ではなく、“調整コストの削減”である」と述べました。本質的な業務の非効率は、現場作業に潜むムダよりも、部門間や関係者間の“すり合わせ”に起因する「調整」にあるのです。
では、その「調整コスト」とは一体何なのか?今回は、その正体をもう少し具体的に掘り下げてみます。
見えない“コスト”の内訳
調整コストとは、組織内で業務を遂行する際に生じる「目に見えない非効率」の集合体です。特に次の3つのタイプに分類できます。
1. 業務間のすり合わせコスト
部門間で連携が必要な場合に発生する「意図の確認」「依頼内容の再説明」「前提のすり合わせ」などのコストです。たとえば、営業部が顧客要望を開発部に伝える際、「なぜこの機能が必要なのか」を繰り返し説明しなければならない。開発部も、社内の技術制約や優先順位を説明する必要がある。双方が納得するまでには、往復で何度もミーティングが行われる――これが典型的なすり合わせコストです。
2. 情報の伝達・確認コスト
業務上の情報が複数の場所・人にまたがって存在し、それを統合・確認するためにかかる時間や労力です。たとえば、「正しい顧客情報はどれか?」「この仕様は最新版か?」といった確認作業に多くの時間が取られてしまうことがあります。これは、情報の一元化や業務ルールの未整備が原因です。
3. 承認・意思決定の遅延コスト
稟議や意思決定が複雑・形式的になっており、スムーズに物事が前に進まない状態を指します。承認者が複数いる、判断基準が曖昧、責任を持ちたくないという心理が働くことで、意思決定はしばしば「先送り」されます。
これらすべてが、“業務そのもの”には直接関係しないコストであるにもかかわらず、業務時間のかなりの割合を占めているのです。
調整前提で設計された業務の怖さ
多くの組織では、「調整が必要なこと」を前提に業務が設計されています。たとえば、曖昧な業務指示を出して「不明点があれば個別に確認してください」と言う運用。業務マニュアルの末尾に「最終的な判断は上司に確認のこと」と書かれているのもそうです。
このように、“調整で補う設計”が定着してしまっているため、調整の回数や手間が減らない。しかも、調整に関わる時間は予算に計上されることもなく、KPIにも反映されません。だから、「見えないまま温存される」のです。
さらに問題なのは、これが“仕方のないこと”として受け入れられている点です。
•「確認に時間がかかるのは当然」
•「稟議は通すのが仕事のうち」
•「他部門との調整は苦労するもの」
このような前提の上に業務が成立している限り、どんなに表面的な業務改善をしても、根本的な効率化には繋がりません。
調整が積み上がると「遅延」と「属人化」が生まれる
調整コストが慢性化すると、最も影響を受けるのは「スピード」と「再現性」です。
まず、業務スピードは間違いなく遅くなります。決定が遅れる、着手が遅れる、確認が終わらない――いずれも調整の副作用です。特に顧客対応が必要な部門では、「社内の調整で時間がかかってしまい、顧客への回答が遅れる」という現象が頻繁に起こります。
また、調整は往々にして「経験のある人」や「顔の利く人」が担うため、属人化が進行します。結果として、その人がいないと回らないプロセスが生まれ、業務の再現性・継承性が損なわれます。
なぜ削減が難しいのか?
最大の問題は、「調整が“やりとり”に見えるため、業務としてカウントされにくい」という点です。調整はSlackやメール、ミーティング、口頭で行われるため、Excelやシステム上には現れません。これが“業務の盲点”となり、改革対象から漏れてしまうのです。
また、調整には「人間関係の維持」や「組織文化の尊重」といった側面もあるため、「なくすこと=不和を生む」と誤解されやすい面もあります。しかし、本来は“仕組み”によって不要にできる調整を、あたかも「必要悪」であるかのように放置している状態が問題なのです。
次回予告:構造が原因なら、構造を変えるしかない
ここまでで、調整コストがなぜ業務改革の最大の障壁となっているのかをご理解いただけたかと思います。では、この見えないコストをどう可視化し、どう排除していけばよいのでしょうか?
その鍵となるのが、「ビジネスプロセスの構造化」です。
【第3回】では、調整コストを生む業務構造の特徴と、それを変えるために必要な「モデリング」の考え方について掘り下げていきます。
第1回:第1回業務改革の「大いなる誤解」〜無駄取りだけでは変わらない〜
合同会社タッチコア 代表 小西一有
