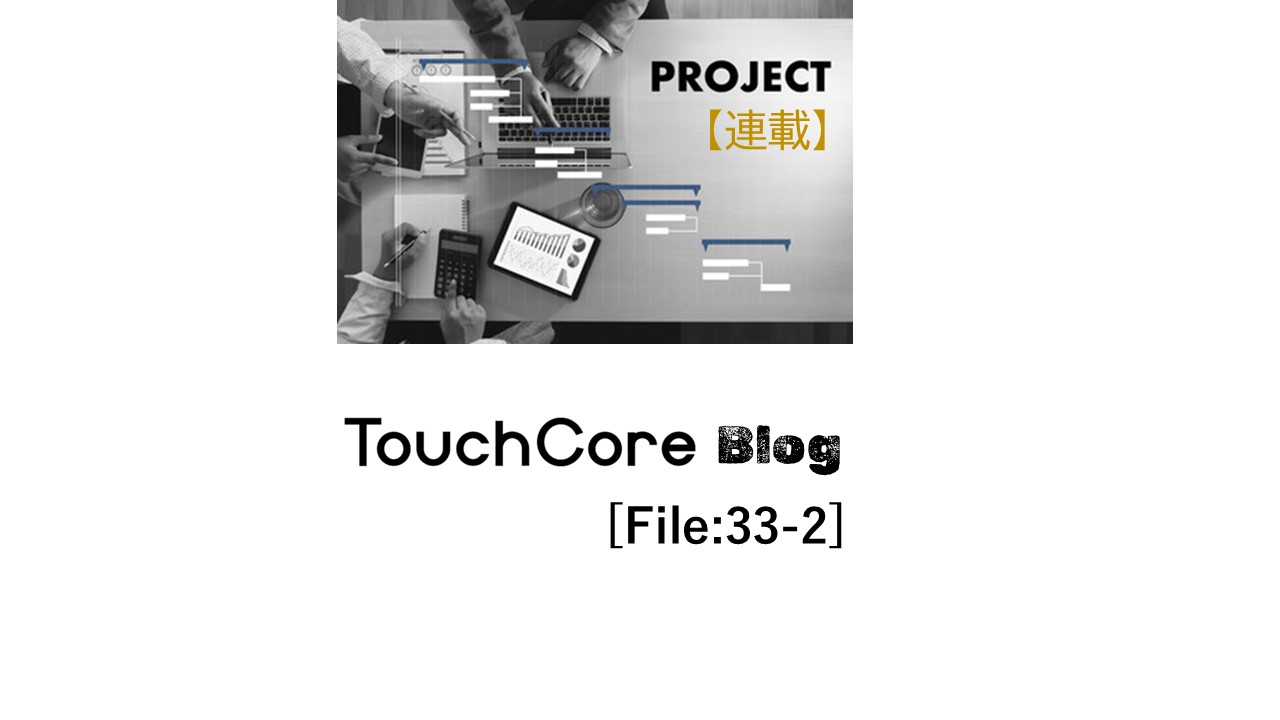
はじめに
PMOは雑務係でも、報告整備部隊でもありません。では、PMOが本来担うべき役割とは何でしょうか?それは一言でいえば、「変革推進のための知的支援機関」として機能することです。
前回の記事で述べたように、PMOはしばしば「便利屋」として扱われますが、それはプロジェクトの本質的な課題に対して思考を深める機会を奪う結果にもなり得ます。今回は、PMOが本来果たすべき知的・心理的役割について掘り下げていきます。
「変革推進」とは何か?現場の沈黙に耳を澄ませる
「変革推進」と聞くと、PMOが現場を引っ張って改革を主導するようなイメージを持つかもしれません。しかし、実際の変革は、現場一人ひとりが「これは変えなければ」と自分ごととして気づき、動き始めることで初めて起こります。
PMOの役割は、この「気づき」を生む環境を整えることにあります。つまり、
•現場がモヤモヤを抱えているのに言語化できない
•言いたいことがあるが、空気的に言い出しにくい
•やるべきことはわかっているが、どこから手をつければいいか迷っている
といった“沈黙した声”に気づき、言葉にするプロセスを支えるのがPMOの価値です。
思考を支援するPMOの「問いの立て方」
PMOは、自らが答えを出すのではなく、関係者の中にある知恵や気づきを引き出すために「問いを立てる」役割を担います。たとえば、次のような問いを投げかけることで、議論を促進します:
•「この方針は、誰にとって、どんな意味を持つでしょうか?」
•「現場のこの行動には、どんな背景や事情があると思いますか?」
•「今このタイミングで決めるべきことと、先送りしてよいことを分けてみましょうか」
こうした問いは、関係者の視野を広げ、主観と客観の切り替えを促します。それにより、プロジェクト内で対話が進み、合意形成が進みます。
PMOがただの調整役ではなく、知的ファシリテーターであるという認識は、こうした問いを扱えるかどうかにかかっているのです。
「対話」と「見える化」で現場の思考を進める
変革を進めるためには、言語化されていない問題を「言葉」にし、可視化されていない構造を「図」にする力が必要です。これは、単なるドキュメンテーションスキルではなく、思考支援のスキルです。
たとえば:
•プロジェクトのステークホルダー関係を1枚の関係図に落とし込む
•モヤモヤしているリスクを「発生要因」「影響」「対応」の3軸で整理する
•会議の中で出てきたアイディアをその場でホワイトボードに図解する
こうした行為が、関係者に「そういうことだったのか」と腹落ちさせ、行動のスイッチを押します。PMOが行うべきは、「説明」や「説得」ではなく、「納得を生む場づくり」です。
心理的安全性を整える見えない仕事
多くのプロジェクトでは、関係者が「本当は言いたいけど言えない」「わかっていないけど、聞くと無知だと思われそう」という心理的圧力の中で動いています。PMOが果たすべき価値の一つは、こうした心理的障壁を下げ、誰もが「言っていい」「聞いていい」と思える場づくりをすることです。
これは定量的に測れない、見えにくい仕事ですが、これがなければプロジェクトは表面的な合意のまま進み、実行段階でつまずきます。PMOがファシリテーターとして機能するとは、単に会議を仕切ることではなく、「話す勇気」を支える心理的安全性を設計することに他なりません。
成功の影にいるPMOの姿
多くの優れたプロジェクトの裏側には、「声を拾う人」「構造を整える人」「視点を切り替える人」がいます。彼らは表舞台には出ないかもしれませんが、その存在なくしてプロジェクトは成立しません。
PMOは、そのような「成功を支える裏方」として、ただの調整役ではなく、知的ファシリテーターであり、心理的安全性を設計する支援者であるべきです。
次回は、こうした役割を担うPMOメンバーが、なぜ現場で疲弊し、孤立してしまうのか。その心理的構造について深掘りしていきます。
第1回:なぜPMOは誤解されるのか?~雑務係に成り下がる構造
合同会社タッチコア 代表 小西一有
