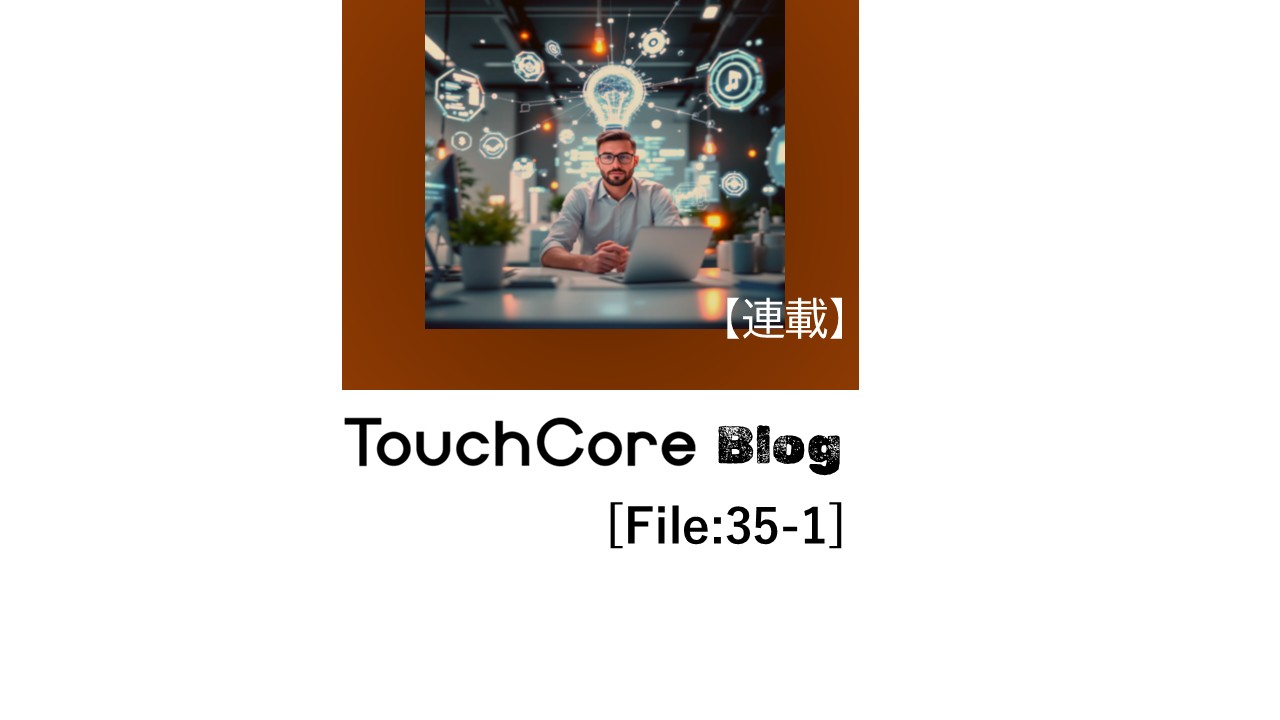
イノベーション創造講座を始めた理由
私はこれまで、さまざまなイノベーションコンテストで審査員や講師として声をかけていただく機会に恵まれてきました。そこに集まる方々は、いずれも真剣に課題と向き合い、解決の糸口を探しているという点で素晴らしいのですが、正直に申し上げると、発表されるアイディアの多くに「ときめき」がないと感じてしまうのです。
もっと端的に言えば、「それ、よくあるよね」という発想ばかりなのです。
私は、アイディア勝負の場であるならば、「その発想は、自分には思いつかなかった…」と驚かされるようなものがなければ、本当の意味での評価には値しないと考えています。どんなにプレゼンが上手でも、着地の見込みが高くても、「思考の軌跡」が平凡であれば、それはただの現状延長にすぎません。
ここで誤解してほしくないのは、「奇をてらえばよい」という話ではないということです。私が問題視しているのは、多くの人が「実現できそうなことしか考えていない」という姿勢そのものです。今ある技術、今の制度、今の社会構造の中で“何ができそうか”を出発点にする思考では、世界を変えるアイディアにはたどり着きません。
現代社会には、サステナブルな課題をはじめとして、解決困難な問題が山積しています。そうした本質的な問題を乗り越えるためには、「いま出来ること」ではなく、「本当にすべきことは何か?」という問いを立てる力が不可欠です。
だからこそ私は、「常識を逸脱して非凡なアイディアを次々と出せる人」こそ、社会に必要とされる人材だと考えています。そして、そうした人材は訓練によって育てることができる。そう信じて、5年前から「イノベーション創造講座」を開講しています。
方法論と実践の両輪で鍛える
この講座では、「ただアイディアを出しましょう」などという曖昧なことは一切しません。むしろ、再現可能な発想法を体系的に学び、かつ異なる業種・立場の方々と何度も演習を重ねることで、参加者それぞれの中に独自の発想パターンが構築されていく設計になっています。
たとえば、「ブレインストーミング」と称して職場でガヤガヤと雑談するような光景をよく見かけますが、残念ながら、ほとんどのケースでは本当の意味でのブレストにはなっていません。ただ“批判を控える”だけでは、創造的なアイディアなど生まれないのです。
当講座では、「ラベリング法」や「視点転換」「アイディアの構造化」といった具体的な手法を学び、それを実践的に使いこなす力を身につけていただきます。そして、批判的思考(クリティカルシンキング)も含め、思考の柔軟性と深さを両立させるトレーニングを行います。
こうした力は、起業家や研究者だけに必要なものではありません。日々の業務改善、商品企画、サービス設計、チーム運営など、あらゆる職種・業務で「よりよい選択肢を考える力」として活かされるのです。
「知らないからできない」からの脱却
私が強く危惧しているのは、日本の教育や職場環境の中で、「アイディアの出し方」や「創造的思考」がほとんど教えられていないという現実です。だからこそ、多くの人が“誤って”理解してしまい、「自分にはセンスがないから」「創造的なことは苦手」と思い込んでしまう。
これは本当にもったいないことです。
思考の訓練は誰でもできる。
必要なのは、正しい方法論と、それを実践する場です。
私がこの講座を立ち上げたのも、「何とかしなければ」という切実な思いからでした。幸い、コロナ禍を機に全15回の講座をオンラインで提供できるようになり、今では日本全国から多様な背景の方々が参加してくださっています。
そして多くの受講生が、講座終了後には「発想が変わった」「仕事の見え方が変わった」「会議での発言の質が変わった」とおっしゃってくださいます。
常識を逸脱する」ってどういうこと?
次回は、私が講座で特に重視している「常識を逸脱する力」について、もう少し具体的にお話ししたいと思います。単なる逆張りではない、「構造的に考える」ことによって初めて到達できる発想の世界を、ぜひ覗いてみてください。
||申込み受付中||
2025年10月期「イノベーション創造(アイディア創出)講座」
合同会社タッチコア 代表 小西一有