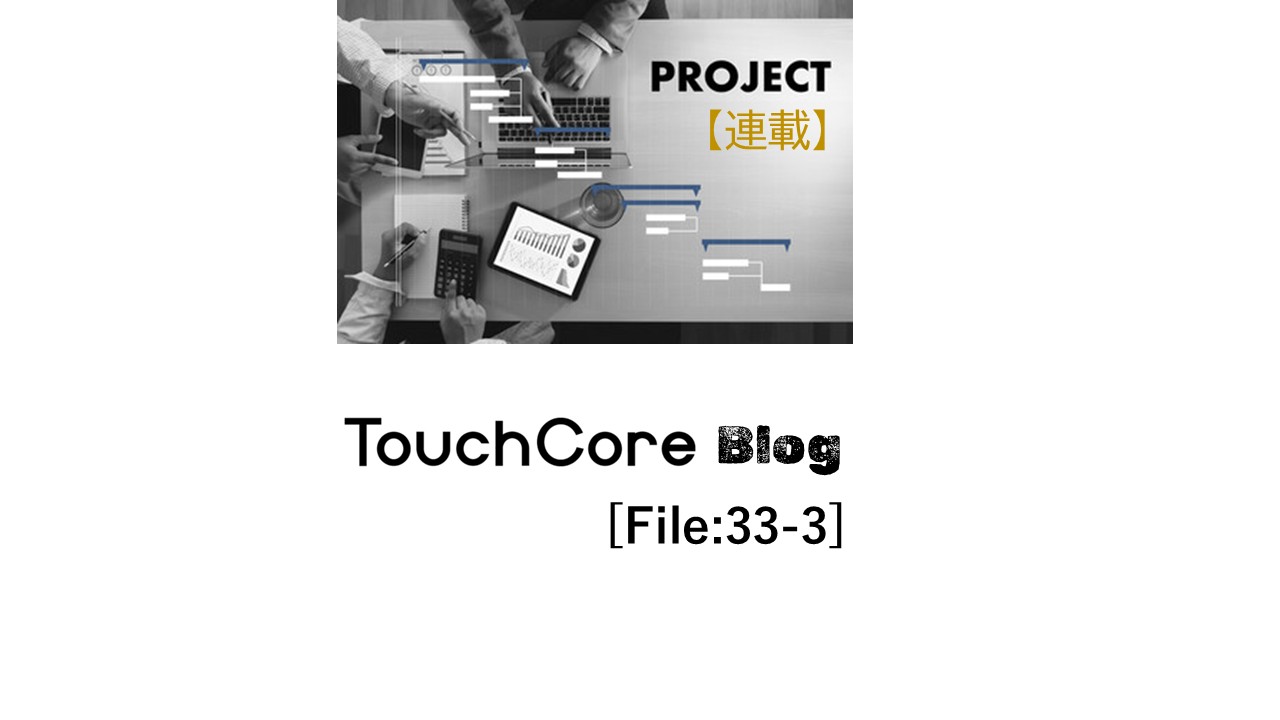
はじめに
PMOがプロジェクトを知的に支える存在であるべきだという理想に対し、現実のPMO要員たちはしばしば「疲弊」し、「孤立」しています。
•頑張って資料をまとめても「便利屋」扱い
•現場を支援しようとしても「邪魔者」扱い
•意見を言おうとしても「それは君の立場じゃない」と言われる
このような声は、現場のPMOから日々聞こえてきます。なぜ、PMOという組織に期待が集まりながらも、そこに所属する人たちが心をすり減らしてしまうのでしょうか?
今回は、PMO要員の心理的な孤立と葛藤の構造をひもときながら、その背景にある「役割のあいまいさ」と「期待の分裂」について考えます。
「あいまいな役割」に振り回されるPMO
PMOの仕事は、明確に定義されていないことが多いです。「プロジェクトを円滑に進めるための支援をする」という言葉は便利ですが、抽象的で、人によって期待する内容が大きく異なります。
•現場は「代わりにやってくれる人」として期待する
•マネジメント層は「状況を整理し、可視化してくれる人」として見る
•PMO本人は「本質的な支援がしたい」と思っている
このように、立場によって「PMOに期待するもの」が異なり、それがすり合わせられないまま業務が始まることで、PMO要員は常に「誰かの期待を裏切っているような感覚」に陥ります。
この状態が続くと、「何をやっても中途半端」「誰の役にも立っていないのでは」といった無力感に襲われ、心理的に疲弊していきます。
「空気を読む」が、対話を殺す
もう一つ、PMOが抱える心理的負荷の大きな要因は、「組織の空気を読みすぎる」ことです。
PMOは、プロジェクト内の多くの利害関係者と関わります。そのため、「誰かを怒らせてはいけない」「場の雰囲気を壊してはいけない」という無意識の圧力が強くかかります。
•上司の意図に反しないように議事録を書く
•会議の空気が険悪にならないように論点をぼかす
•異論があっても「現場のためには黙っていた方が良い」と飲み込む
こうした行為は、場の秩序を保つように見えて、実は思考や対話の機会を失わせています。PMO自身も、「本当は違うと思っているのに、それを言えない」ストレスにさらされ続けることで、内面で分断を抱えます。
「共感しすぎる」ことの危うさ
PMO要員は、他者に共感する力が高い人が多いです。現場の苦労を理解し、マネジメントの要求も理解し、両者の間に立って調整する。しかし、その「共感力」が行きすぎると、他人の問題まで自分の責任として背負い込んでしまいます。
•「現場の人が困っているから、自分がやるしかない」
•「マネージャーが期待しているから、応えなければ」
•「誰かが不満を言う前に、問題を先回りして潰しておこう」
このように、「自分が何とかしなければ」という思考に陥ると、PMOは自らの健康と余裕を犠牲にしてしまいます。結果として、誰からも「ありがとう」と言われず、誰にも「相談」できず、孤独の中で働くことになります。
「わかってくれる人がいない」という孤立感
PMOの仕事は、成果が目に見えにくく、また成果を出したときには「問題が起きなかった」ために誰も気づかないことが多いです。そうすると、達成感や承認を得る機会が少なく、「自分の存在価値がわからなくなる」状態に陥りやすくなります。
特に、一人PMO、あるいは少人数PMOの環境では、この孤立感が深刻です。メンバー内で「愚痴」や「悩み」を共有する場もなく、自己否定感が積み重なっていきます。
PMOを支える「内省」と「対話」の場の必要性
PMO要員が心をすり減らさずに、知的支援者として機能するためには、本人の「内省」と、他者との「対話」が欠かせません。自分の役割を定義し直し、どこまで関与し、どこからは他者の責任とするかの境界を意識的に考えることが重要です。
そして、PMO同士で悩みや工夫を共有するコミュニティやメンタリングの場が必要です。孤立した状態では、PMOはいつか「ただの作業者」に埋もれてしまいます。
次回は、そうした「孤立」や「誤解」を乗り越え、PMOが現場と信頼関係を築きながら、自らの役割を再構築していくための「ふるまい」について掘り下げていきます。
第1回:なぜPMOは誤解されるのか?~雑務係に成り下がる構造
第2回:PMOが担うべき「変革推進」と「思考の支援」
合同会社タッチコア 代表 小西一有
