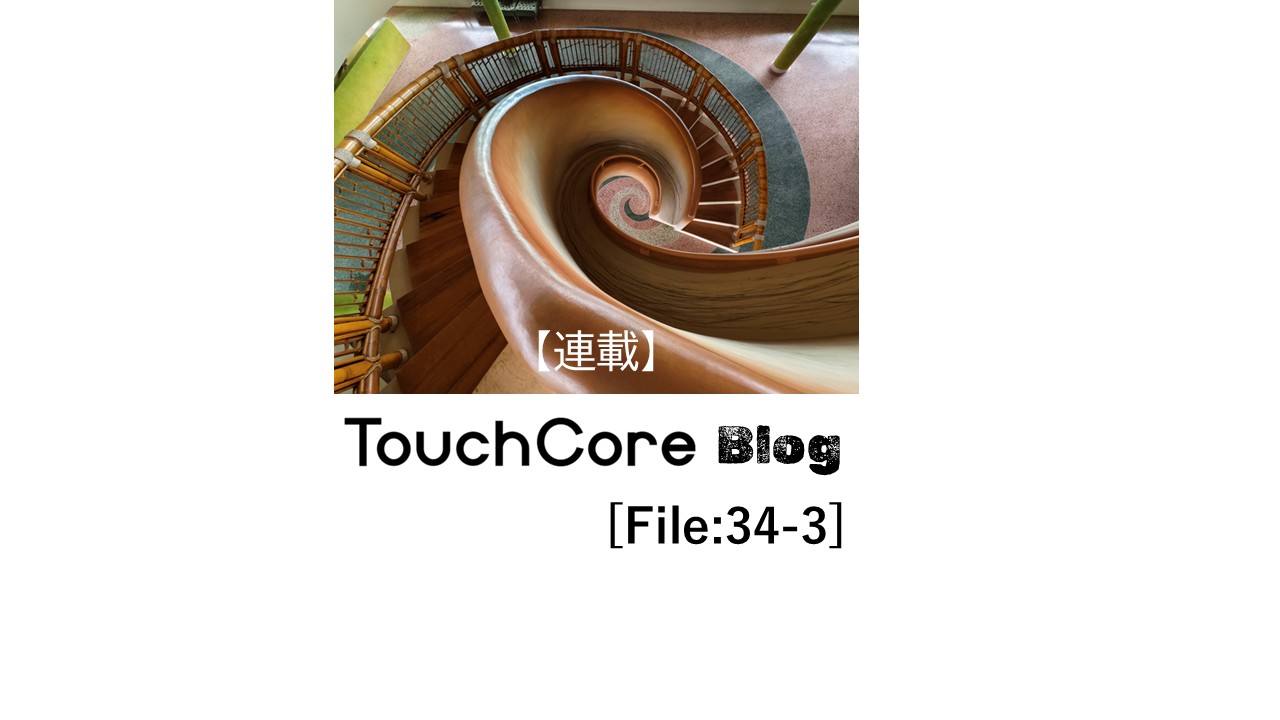
はじめに:事務作業に潜む“見えないコスト”とは?
事務作業における非効率の多くは、「作業そのもの」ではなく、「調整」によって発生しています。
•「この件、どうなっていますか?」という確認
•「先に処理してほしい」とお願いする催促
•「これって何をしたらいいの?」という意図のすり合わせ
•「こっちの処理は終わっているのに、向こうがまだ」といった待機状態
これらのやり取りには時間とエネルギーがかかります。さらに、関係者が多くなると、確認や合意のために多重のコミュニケーションが必要となり、全体としての処理速度はどんどん遅くなっていきます。
ここでこそ、「一個流し」の効果が発揮されるのです。今回は、一個流しが調整コストの削減と意思決定の加速にどう寄与するかを、3つの切り口から掘り下げていきます。
手待ち時間をなくせば調整そのものが不要になる
まず、バッチ処理の最大の欠点は「仕事が途中で止まってしまう」ことです。
たとえば、以下のような状態を想像してください:
•書類が承認者の机の上で3日間滞留
•入力済みのデータが誰かの確認待ちでシステムに登録されない
•顧客対応が担当者の休暇で止まっている
こうした「仕事が動かない状態」を解消するために、上司・同僚・他部署との調整行為が生まれます。しかもこれは一度だけでなく、催促・報告・確認といった複数回のやり取りが必要になることが多く、膨大な時間が浪費されているのです。
「一個流し」を前提に仕事を設計すると、「止めないこと」が最優先になります。
そのために、以下のような施策が自発的に出てきます:
•承認プロセスの短縮(その場で判断、移譲、事前承認)
•確認作業の標準化(例:チェックリストや自動判定)
•不在時の代理ルールの明確化(“引き継がずに止まる”を防ぐ)
結果として、「調整しなくても、仕事が進む」状態が実現します。
マルチタスクをやめれば判断の質が上がる
人間の脳は、同時並行に複数の作業を処理するようにはできていません。マルチタスクの状態では、判断力・注意力・記憶力すべてが低下します。
バッチ処理が常態化している職場では、たいてい以下のような状態が起きています:
•メールを見ながら資料を作り、電話が鳴って思考が中断し、また資料に戻る
•依頼されたタスクを一時保留にして別の案件を優先し、元の仕事の内容を忘れる
•進捗確認のための会議で、「それって何の件でしたっけ?」と記憶を手繰る
こうした“細切れ処理”を防ぐには、「一個ずつ、集中してやり切る」しかありません。
一個流しを実践すると、以下のような行動が根付きます:
•ひとつの仕事に集中 → 判断が早く、確実になる
•処理単位が小さい → 内容が頭に残っており、説明・報告がしやすい
•次にやることが明確 → 優先順位のすり合わせが不要
つまり、判断と連携の品質が高まり、調整の回数そのものが減るのです。
「仕事の流れ」が見えると、連携が言葉なしに成立する
「一個流し」は仕事の透明化にもつながります。
たとえば、カンバン方式や共有ToDoリストを活用して仕事の流れを見える化しておくと、以下のようなことが可能になります:
•次の担当者が、自分の出番を「指示されなくても把握できる」
•マネージャーが、仕事の進捗を見て必要な支援や調整を早期に行える
•業務の分担や負荷の偏りを、チームで客観的に評価できる
これは、“言われてから動く”のではなく、“流れてきたから動く”という状態。つまり、人が人を動かすのではなく、仕事の流れが人を動かす状態が実現します。
このように、仕事の“流れ”を可視化し、自然に動ける構造を整えることが、調整の必要性をそもそも減らしていくのです。
まとめ:調整に時間を使わない組織へ
調整コストとは、「人と人の摩擦によって発生するムダ」です。
•手待ち
•確認
•記憶の呼び起こし
•催促
•誤解のすり合わせ
これらは本来、やらなくてもいい仕事です。
「一個流し」を徹底すると、こうした“調整のための労力”が激減します。
そして空いた時間と思考の余白を、本当に価値ある仕事(思考、企画、対話、改善)に振り向けることができるようになります。
第1回:「一個流し」は製造業だけの話じゃないー事務作業にも効くTPSの原則
第2回:「一個流し」を事務作業に適用するには?ー業務単位の見直しと“流れ”のデザイン
合同会社タッチコア 代表 小西一有
