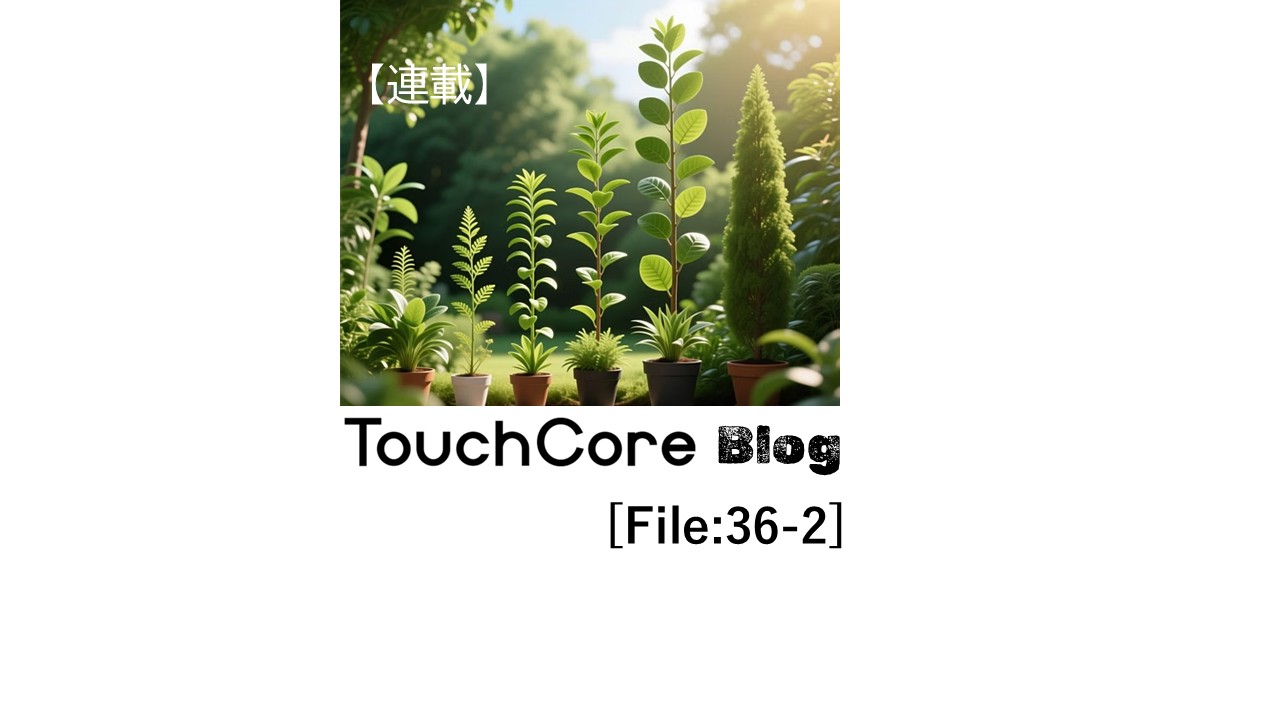
前回は「ビジネスモデル=価値の実装である」という視点から、中小企業こそがビジネスモデル変革によって競争優位を築けると述べました。では、なぜ日本企業はこれまで“ビジネスモデル”という考え方を深く掘り下げてこなかったのでしょうか?
その理由のひとつは、日本が長らく「モノづくりの国」であったという成功体験にあります。
製品と品質で勝ってきた日本
戦後の高度成長期、日本は製造業を中心に国力を築きました。世界が驚くような品質の自動車、家電、精密機器をつくり出し、「良いモノを作れば、売れる」という時代がありました。
このときの成功体験が、日本企業の根幹に深く刻まれています。
製品開発=事業の中心
品質管理=競争優位の源泉
現場改善=経営の要
このような構図においては、「仕組み」や「収益構造」よりも、「製品」や「現場」に目が向いてしまうのは自然なことだったのです。
ビジネスモデルは“外道”だった
日本企業にとって「ビジネスモデル」という言葉は、長らく違和感のあるものでした。
なぜなら、戦略とは「泥臭く現場で培うもの」という意識が強く、どこか“頭でっかちな戦略論”や“MBA的なお勉強”と見られていたからです。
「現場を知らずに経営ができるか」
「机上の空論より、1件の営業」
こうした価値観は、今なお多くの経営層に共有されています。もちろん現場志向は日本企業の強みですが、それが「構造を変える」という思考の妨げにもなっているのです。
「製品志向」から「価値志向」への移行に失敗した
グローバル市場が成熟し、競争が激化する中で、単なる製品品質では差別化が難しくなってきました。
世界では、早くから「体験」「関係性」「ビジネスモデル」へのシフトが進んでいました。Appleのエコシステム戦略、Netflixのサブスクリプション、Airbnbのプラットフォームモデルなどが代表例です。
しかし日本企業の多くは、「良い製品をどうやって売るか」という発想から脱却できませんでした。
その結果、製品は良くても“選ばれない”“使い続けられない”という現象が起きたのです。
設計思想の欠如が「仕組みの凡庸さ」を生む
製品には設計図があり、品質基準があるのに、ビジネスモデルにはそれがありません。なぜなら、多くの企業が「設計思想」そのものを持っていないからです。
•なぜこの価格なのか?
•なぜこの提供方法なのか?
•なぜこの顧客接点なのか?
これらの問いに、論理的かつ意図的に答えられる企業は少数派です。多くは「なんとなく」「業界慣習として」「昔からこうだから」という理由で構造が形成されています。
つまり、ビジネスモデルが“自然発生的”に存在しており、“戦略的に設計されていない”ということです。
「モノ→コト→トキ」へのパラダイムシフト
これからの時代に求められるのは、「モノ(製品)」ではなく、「コト(体験)」であり、さらに「トキ(時間の価値)」をどう提供するかです。
たとえば、同じカメラでも…
•モノ:高画質・高機能なカメラ
•コト:思い出を美しく残す体験
•トキ:家族と過ごす“今”の大切さ
このように、商品そのものよりも、その商品がもたらす“時間の価値”や“意味づけ”に顧客はお金を払うようになっています。
しかし、こうした視点の転換は、単なるマーケティング施策では不十分で、ビジネスモデル全体を見直すことが必要になります。
中小企業こそ「設計し直す勇気」を持とう
大企業ほど複雑な事情がない中小企業は、実はこの「設計思想の転換」を一気にやりやすい立場にあります。市場を狭く絞り、顧客接点を強くし、柔軟な収益構造を試す──こうしたことは大企業には真似できません。
今必要なのは、「製品を磨く努力」ではなく、「価値を届ける構造」をデザインし直す勇気です。
次回予告:
第3回「『デジタル=業務効率化』ではない!」では、
デジタル技術を「コスト削減」ではなく「価値創造」に転化する方法を、ビジネスモデルの観点から解説します。
合同会社タッチコア 小西一有
第1回:なぜ中小企業はビジネスモデルを変える必要があるのか?ー価値を実装するための視点転換
||申込み受付中!||