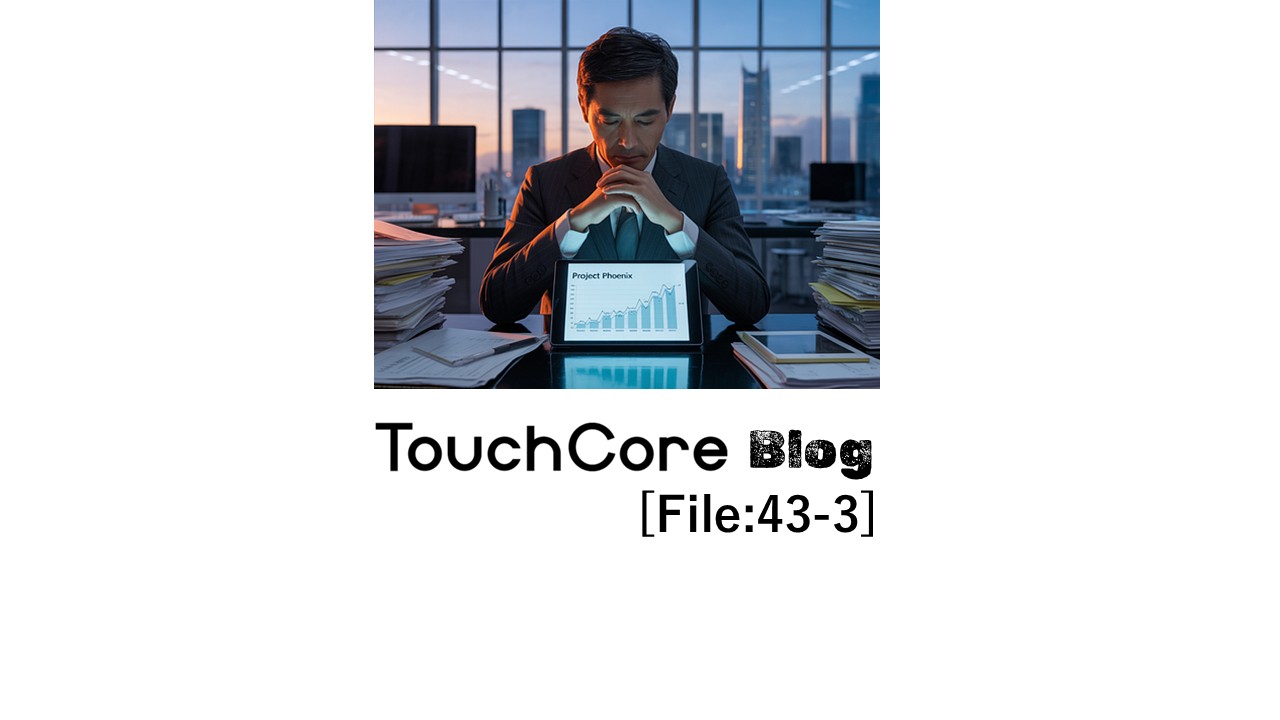
「やるリスク」と「やらないリスク」。
経営者が意思決定を迫られるとき、頭をよぎるのは必ずこの二つの天秤です。
ところが多くの場合、私たちは「やるリスク」を過大に見積もり、「やらないリスク」を過小評価してしまいます。その結果、たとえ正しい情報を受け取っても、「今はまだ動かないほうが安全だ」と結論づけてしまうのです。
本能としてのリスク回避
心理学的に言えば、人間は「損失回避バイアス(loss aversion)」に支配されています。1円を失う痛みは、1円を得る喜びの2倍以上に感じられる――これは数々の実験で明らかになっています。
つまり「失敗したらどうしよう」という不安は、「成功したらどうなるだろう」という期待よりも強烈に作用するのです。経営者も人間である以上、このバイアスから逃れることはできません。
そのため、たとえデータが「投資すべきだ」と示していても、「万一失敗したら自分の責任になる」と恐れて行動を止めてしまいます。
「やらないこと」もリスクである
しかし、本来は「やらないこと」も大きなリスクです。技術革新のスピードが速い現代では、意思決定を先送りするだけで競争優位を失いかねません。
典型的なのはデジタル化の波です。既にクラウドやAIが当たり前となっているにもかかわらず、「導入失敗のリスク」を恐れて投資を先送りする企業は少なくありません。ところがその間に競合は着々と基盤を固め、差は広がる一方です。
つまり「やらないこと」自体が、見えにくいリスクとしてじわじわ経営体力を蝕んでいくのです。
日本企業に根強い「責任回避」の文化
さらに日本的な特徴として、「責任回避の心理」があります。
「誰がやると言ったのか?」
「失敗したら誰が責任を取るのか?」
こうした議論が先に立ち、本質的なチャレンジの議論が後回しになる。結果として、経営者自身も「いま決断すると責任を一人で負うことになる」と恐れ、正しい情報を理解しながらも動かない――そんな構造が生まれます。
この責任回避の文化は、役員会や株主との関係、さらには社内の同調圧力とも結びつき、経営判断を硬直化させていきます。
行動できる経営者は「リスクを相対化」する
では、どうすればよいのでしょうか。
・「やらない場合、3年後にどうなっているか?」
・「小さな実験であれば、失敗コストはどの程度か?」
・「リスクを分散する手段は何か?」
このように具体的に比較することで、リスクの輪郭が浮かび上がり、「やらないリスク」の深刻さも見える化できます。結果として、リスクをゼロにするのではなく「コントロールする」という視点が芽生え、意思決定が可能になるのです。
まとめ
経営者が正しい情報を前にしても動けない理由の一つは、「やるリスク」を過大に見積もり、「やらないリスク」を過小評価する心理にあります。
次回は、さらに外部要因として働く「組織の同調圧力と孤独」について掘り下げます。
合同会社タッチコア 小西一有
第1回:なぜ「正しい情報」があっても動けないのか
第2回:過去の成功体験という“呪縛”