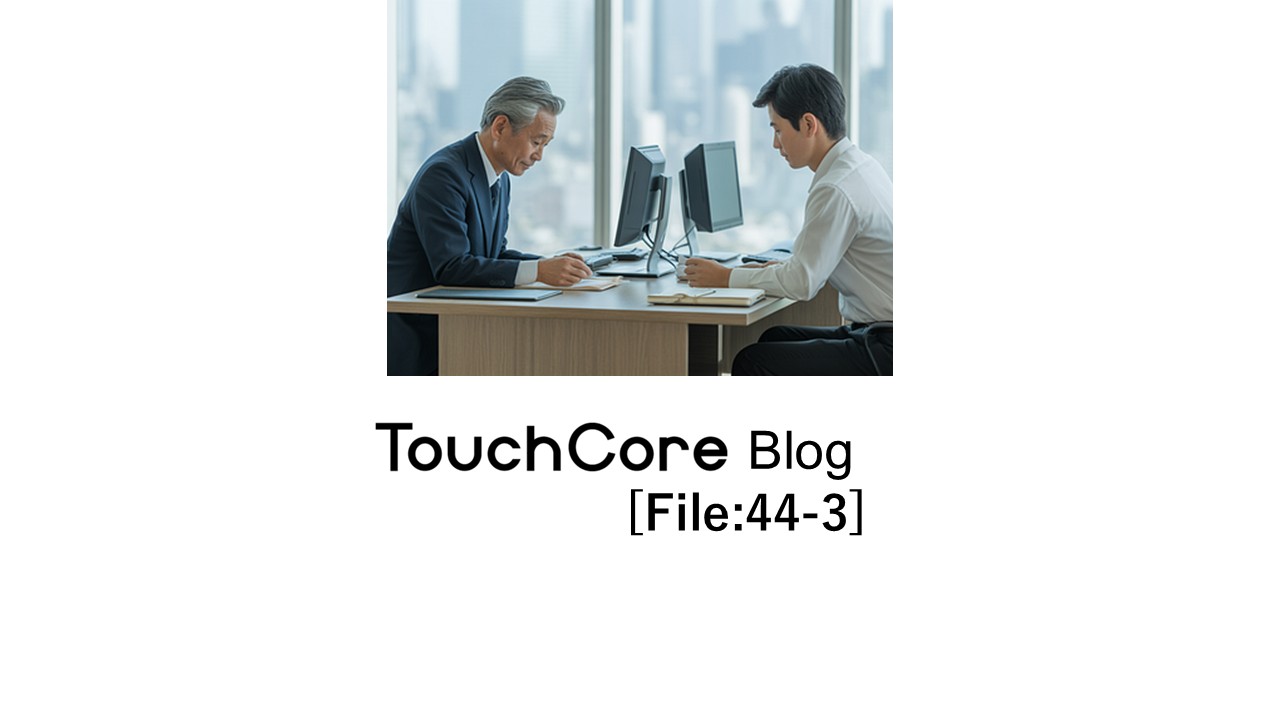
近年、日本ではIT企業が数多く生まれ、急成長を遂げてきました。その多くは優秀な技術者が起業し、経営者となった会社です。彼らは技術に関しては圧倒的な知識と経験を持っています。
しかし、私は数多くの現場を見てきて、ある共通の問題に気づきました。
「技術に強いが、経営や人を率いる力に乏しい」―これが、技術者出身の経営者が陥りやすい罠です。
技術力が高い=経営ができる、ではない
技術者出身の経営者は、往々にして「技術を磨けば会社は伸びる」と信じています。確かにスタートアップの初期にはそれで成功することもあります。革新的な技術で市場に新風を吹き込むことができるからです。
しかし、会社が大きくなり、社員が増えると状況は変わります。技術力だけでは組織を動かせません。求められるのは 戦略を描く力、資源を配分する力、人を率いる力 です。
ところが、多くの技術者出身経営者は、この領域を学んでいないのです。
技術偏重が生む組織のゆがみ
技術に強い経営者
がトップに立つと、会社はどうなるでしょうか。
・経営会議での議論が技術的な詳細に偏る
・営業・マーケティング・人材育成といった領域が軽視される
・社員評価が「技術力」だけに偏る
こうしたバランスの悪さは、組織全体に大きなひずみをもたらします。
とりわけ問題なのは、幹部層もまた「技術至上主義」に染まってしまうことです。経営に必要な視点が欠け、会社が大きくなるほどマネジメントの限界に直面します。
「優秀な技術者」が「未熟な経営者」になる理由
なぜ技術者出身の経営者は、経営に弱いままトップに立ってしまうのでしょうか。
理由のひとつは、日本の教育や企業文化にあります。
理工系の学生は、経営や組織論を学ぶ機会がほとんどありません。入社後も「技術を極めれば昇進できる」環境に置かれます。その結果、経営に必要なスキルを学ぶ前に経営者になってしまうのです。
さらに、技術
者は「正解がある世界」で生きてきました。バグを潰し、論理を積み重ね、正しい答えに到達する世界です。ところが経営には「唯一の正解」はありません。環境や人材に応じて、最適解を選び続けることが求められます。このギャップを埋めるためには、意識的な学び直しが不可欠なのです。
IT企業でよくある失敗例
私はこれまでに、IT企業で次のような失敗を何度も見てきました。
・優れた製品を開発しても、営業力が伴わず市場拡大に失敗
・経営者が現場のコードレビューに没頭し、経営判断が遅れる
・組織が成長しても「管理職不在」で、人材流出が止まらない
いずれも原因は「経営者が経営を学んでいない」ことにあります。
技術者が経営を担うこと自体が問題なのではありません。
問題は、経営者として必要な教育を受けていないまま、トップに立ってしまうことです。
技術部門出身経営者に必要な教育とは
では、技術部門出身経営者が学ぶべきことは何でしょうか。私は次の3つを提案します。
1.経営の基礎理論
財務、組織論、戦略論など、技術とは別の体系的知識を学ぶこと。
2.リーダーシップと人材マネジメント
技術だけでなく、人を動かすための言葉と姿勢を身につけること。
3.未来視点の思考法
AIやデジ
タル技術を単なる「ツール」としてではなく、ビジネスモデルや経営戦略にどう活かすかを考える視座を持つこと。
これらを学び直すことで、技術者は「優れた経営者」へと進化できます。
まとめ:経営者もまた教育を受けるべき存在
技術者がトップに立つIT企業こそ、幹部・経営層の教育が不可欠です。
経営者自身が学ばなけれ
ば、組織は必ず成長の壁にぶつかります。
人材育成とは、若手だけのものではありません。
経営者自身もまた、教育を受けるべき存在なのです。
次回は、AI教育のブームに潜
む落とし穴を取り上げます。
「プロンプト入力を教えるだけの研修」がなぜ不十分なのかを解き明かします。
技術に偏った経営から一歩進み、組織を動かすリーダーへ。
幹部・経営層の教育に課題を感じる方は、ぜひご意見やご相談をお寄せください。
私が伴走し、経営と人材戦略を結びつけるお手伝いをいたします
合同会社タッチコア 小西一有
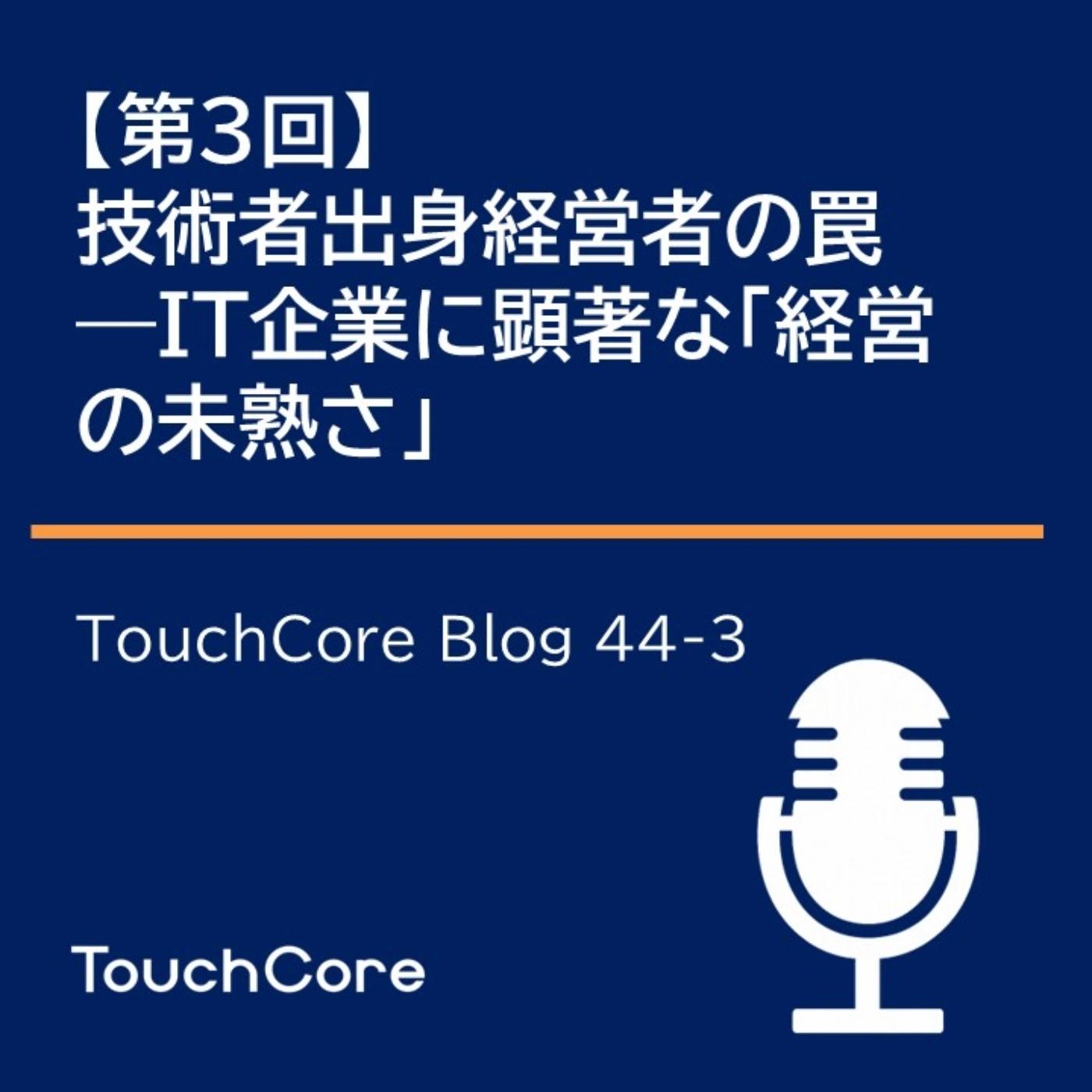
第1回:人材育成の誤解―なぜ若手教育だけでは会社は変わらないのか
第2回:幹部教育こそ最大のレバレッジ―組織を動かす層を鍛える