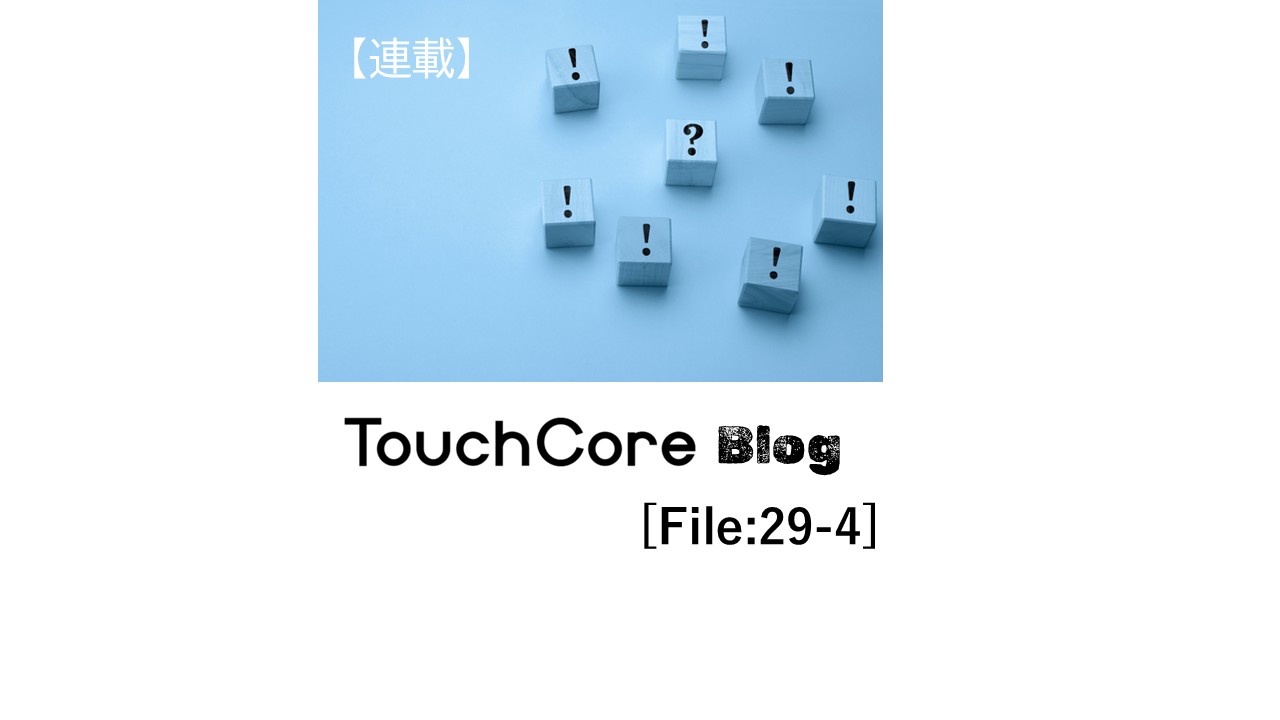
前回までで「調整コストは業務の構造に起因する」「その構造を見える化・明示化しない限り、調整はなくならない」ということをお話ししてきました。 では、実際に業務構造を見える化し、調整を減らすにはどうすれば良いのでしょうか?
答えは、「モデリング」にあります。モデリングとは、業務を単なる作業の羅列ではなく、“プロセス”として設計・記述する行為です。今回は、モデリングによって調整の発生を抑え、業務改革を構造的に進める方法についてお話しします。
モデリングとは何か?
「モデリング」という言葉を聞くと、ITやシステム開発を想像する方も多いかもしれません。しかし、ここでいうモデリングとはもっと基本的な、業務を論理的に整理して視覚化する活動です。
具体的には、以下のような要素を整理・明示化します:
•業務の開始条件(トリガー)
•関与する役割(担当者・部門)
•各タスクで使用・生成される情報
•各タスクの手順と順序(フロー)
•「成果物(アウトプット)」とその受け渡し先
•利用するツールやシステム
•業務の終了条件
これらを図や表に落とし込むことで、業務の全体像を「構造」として理解できるようになります。そして、構造が見えると初めて、調整の発生ポイントが特定できるのです
モデリングがもたらす3つの効果
1. 責任と引き渡しの明確化
調整が起きる最大の原因は、「誰がどこまでやるのかが曖昧」なことです。モデリングによってプロセスごとに「担当者」「開始条件」「完了条件」を定義すれば、境界線が明確になります。
結果として、関係者の間で不要な確認・再調整が減ります。これは、「調整」から「引き渡し」への転換を意味します。
2. 属人性の排除と再現性の向上
「この業務は◯◯さんでないと分からない」という状態は、業務が“暗黙知”に支配されている証拠です。モデリングにより業務が言語化・図式化されれば、誰が担当しても一定の水準で遂行できるようになります。
つまり、再現性が高まり、属人化による調整や引き継ぎの手間が大幅に削減されます。
3. 改善ポイントの発見と共有
モデルにより業務構造が可視化されると、「手戻りが多い部分」「判断が集中するポイント」「承認のボトルネック」などが一目でわかります。これによって、改善の議論が構造的・客観的にできるようになります。
また、関係者間で共通認識を持つことができ、議論や意思決定のスピードも上がります。
モデリングの具体的な手法
代表的な業務モデリング手法には以下のようなものがあります:
•業務フローチャート
最も基本的な方法。業務の順序と条件分岐を簡潔に可視化できます。
•BPMN(Business Process Model and Notation)
業務プロセスを標準的に記述するための国際規格。業務設計に深みが出ます。
•RACIチャート
「誰が責任を持つか(Responsible)」「誰が最終決定するか(Accountable)」「誰が助言するか(Consulted)」「誰に報告するか(Informed)」を明示することで、組織的な役割分担の曖昧さを排除します。
これらは、PowerPointやExcelでも簡単に作成でき、難解なツールや専門知識を必要としません。
モデリングの成功のコツ:100点満点ではなく70点を目指す
モデリングに取り組む際、多くの現場で見られるのが「完璧を目指して挫折する」パターンです。業務は常に変化するものであり、完全に正確なモデルを作ることは不可能です。
だからこそ、最初は『「70点の構造化」を目指す』ことが重要です。大枠の業務の流れや責任範囲を整理するだけでも、調整コストは大幅に減ります。
さらに重要なのは、「現場の当事者」と一緒にモデリングすることです。外部のコンサルタントが勝手に作るのではなく、実際に業務を担っている人たちがモデルを議論しながら作ることで、現場の納得感と実効性が生まれます。
調整コストのない業務は、設計できる 繰り返しになりますが、調整は「仕方ないもの」ではなく、「構造上の不備」から生まれるものです。つまり、それは設計によって回避可能な“設計上のバグ”に過ぎません。
そして、バグは設計図(=モデル)を描き、対話しながら直していけばよいのです。
次回予告:業務改革の本質とは「構造改革」である
次回【第5回】では、本連載の総まとめとして、「業務改革とは構造を変えることである」という原則に立ち返り、なぜ多くの改革が形骸化するのか、そして本当の意味で業務を変えるには何が必要かを考察します。
第1回:務改革の「大いなる誤解」〜無駄取りだけでは変わらない〜
第2回:調整コストとは何か?〜見えないコストの正体〜
第3回:調整コストを生む業務構造 〜“暗黙知”に依存した仕事の危うさ〜
合同会社タッチコア 代表 小西一有
