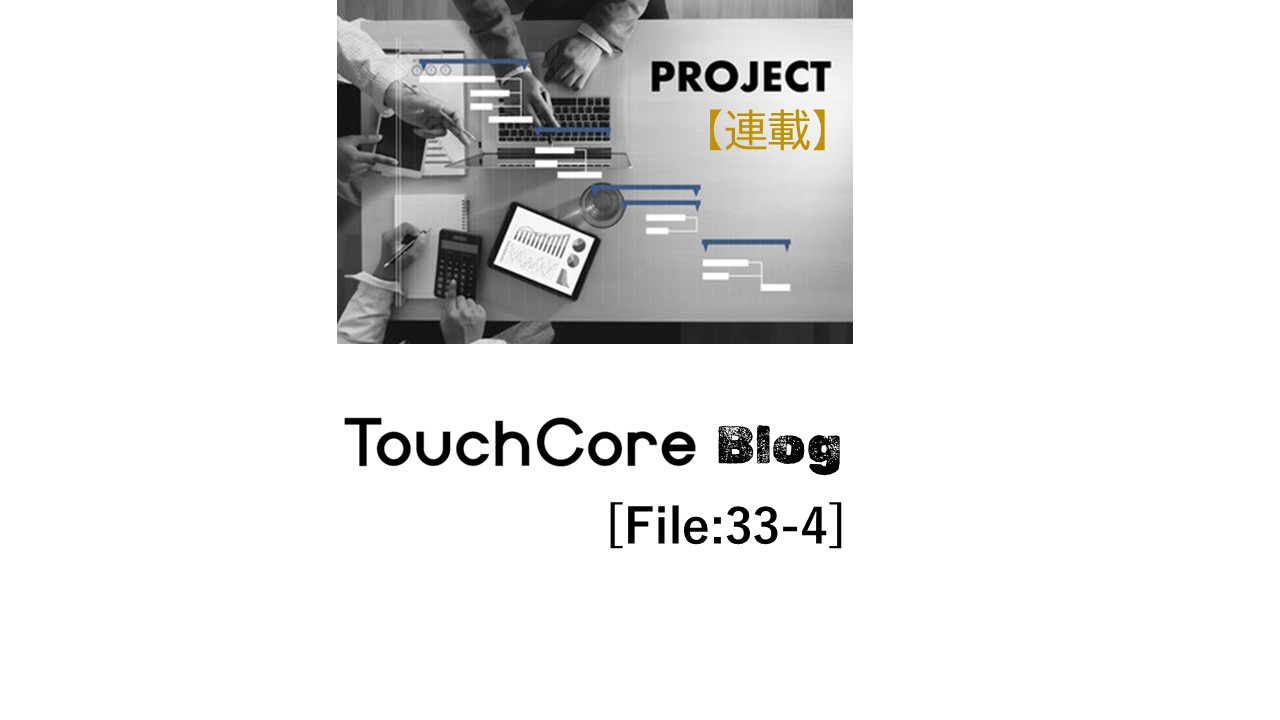
はじめに
PMOが雑務係でも、便利屋でもなく、プロジェクトの知的支援機能であるべきだということは、これまでの記事で繰り返し述べてきました。しかし、いくら正しい考え方を持っていても、現場や上層部からの「信頼」と「納得」が得られなければ、PMOは孤立し、役割を果たすことができません。
本稿では、PMOが組織の中で存在意義を確立し、信頼される存在になるための「ふるまい方」について、特に心理的な側面と構造的視点(モデリング・アーキテクチャ)を交えて考察します。
「信頼される」ことは、「好かれる」ことではない
PMOが目指すべきは「好かれること」ではなく、「信頼されること」です。信頼とは、「この人は筋の通ったことを言ってくれる」「この人と話せば状況が整理される」「この人に任せれば大丈夫だ」と思われること。これは単なる人柄ではなく、「一貫性」「誠実さ」「判断の質」によって築かれます。
気を遣い、空気を読み、対立を避けるふるまいは、一時的な好感は得られても、プロジェクトの本質的な課題に切り込むことはできません。PMOに求められるのは、「違和感を言葉にする勇気」と「本質を問い直す胆力」です
「納得感」を生むには、問い直しから始める
PMOがプロジェクト内で信頼される存在になるためには、「説明」ではなく「納得」を生むことが必要です。そのためには、現場や関係者の言動を単純に受け入れるのではなく、「なぜそうなっているのか?」という問い直しから入る必要があります。
たとえば、
•なぜその作業手順が必要だと思われているのか?
•その会議体は、本当に意思決定機能を果たしているのか?
•そのKPIは、何のために、誰の視点で設計されたのか?
こうした問いによって、思考が再起動し、関係者自身が「目的と手段のズレ」に気づき始めます。PMOがするべきは、上からの指示でも、下からの代行でもなく、「問いを媒介にして、共通の思考を生み出すこと」です。
PMOはしばしば、現場と上層部の間で板挟みになります。両者は、使用する言葉、判断基準、視点の高さが大きく異なるため、互いに誤解が生じやすい構造にあります。
このときPMOが果たすべきは、両者の言葉を「翻訳」することです。
•上層部の抽象的な言葉(例:「KPI」「最適化」「全体最適」)を、現場の具体的な判断軸に言い換える
•現場の具体的な混乱や苦労(例:「どの資料が最新版かわからない」「承認ルートが複雑」)を、構造的・経営的な視点で整理して上層部に伝える
こうした「翻訳」のふるまいは、単なる言い換えではなく、関係性をつなぐ知的・感情的媒介です。どちらの側にも肩入れせず、両者の言葉に「共通の土台」を与える存在として、PMOの価値は発揮されます。
「行動ではなく構造に注目する」ふるまい
PMOがトラブルや停滞の場面に直面したとき、安易に「個人の行動」や「性格」に原因を求めるのではなく、その行動が生まれる構造や前提条件に着目することが重要です。
たとえば、あるメンバーが期限を守らなかった場合、その人を責める前に、次のような問いを立ててみるべきです:
•その人の業務量と優先順位はどうなっているのか?
•必要な情報は誰から、どのタイミングで届く設計になっているか?
•進捗を共有する仕組みやリズムは合理的か?
このように、個別行動ではなく構造的視点から問題を捉え直すことで、PMOは「人を変える」のではなく、「仕組みを整える」方向に貢献できます
モデリング思考を用いた構造の可視化
ここで重要になるのがモデリングや業務アーキテクチャの視点です。プロセス図、情報フロー図、RACIチャート、責任構造モデルなどを用い、行動の背後にある業務設計や組織構造を可視化することで、問題の本質が明らかになります。
例えば:
•業務フローに潜む多重承認や責任不在を図式で可視化する
•ステークホルダー間の情報伝達の断絶を情報フロー図で明らかにする
•「このKPIは誰の意思決定に使われるのか?」を問い、設計の目的を整理する
PMOがこうした構造に働きかける知的中枢としてふるまうとき、初めて「存在してよかった」と実感される役割になるのです。
「感情」を扱う力が、PMOの本質的価値
もう一つ忘れてはならないのが、「感情を扱う知性」です。
多くのプロジェクトで、進行を妨げるのは「人間関係」や「感情のわだかまり」です。PMOは、こうした感情を「見えないノイズ」として処理するのではなく、むしろ「構造の歪みを映す信号」として受け止める必要があります。
•無言の抵抗があるとき、それは何に対する違和感か?
•焦りや苛立ちが噴き出すとき、何が不透明になっているのか?
•担当者が沈黙しているとき、何を口に出せずに抱えているのか?
このような感情を「場」に出すためには、PMO自身が安心安全な雰囲気をつくり、非難せずに受け止める態度を示す必要があります。これは「技術」ではなく「ふるまい」の領域です。
「立場」ではなく「ふるまい」で信頼を築く
PMOが真に信頼されるために必要なのは、部署名や権限ではなく、日々のふるまいの一貫性です。
•話を聞くと状況が整理される人
•問題を否定せず、構造化して返してくれる人
•現場にも上層部にも偏らず、共通の思考をつくる人
そんなふるまいを積み重ねることで、「あの人がPMOでよかった」という言葉が生まれるのです。
次回(最終回)は、PMOを「知的中枢」として再定義し、今後どう組織として設計し、支援すべきか。未来への提言をお届けします。
第1回:なぜPMOは誤解されるのか?~雑務係に成り下がる構造
第2回:PMOが担うべき「変革推進」と「思考の支援」
第3回:第3回 なぜPMO要員は疲弊し、孤立するのか?
合同会社タッチコア 代表 小西一有
