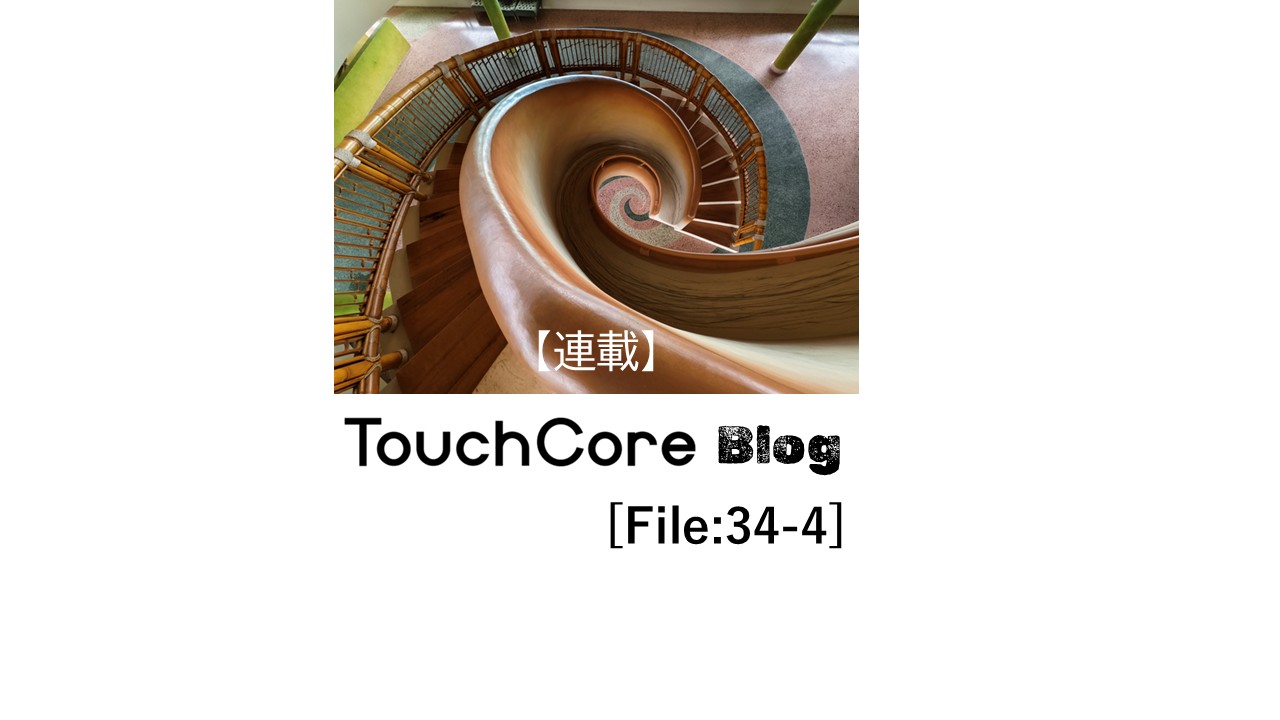
はじめに:技術論だけでは人は動かない
前回までは、「一個流し」を導入することで得られる業務改善効果について、処理スピード・調整コスト・可視化・判断力といった観点から解説してきました。
しかし、実際に職場で導入を試みると、「理屈は分かるけど、現場が動かない」という壁にぶつかることが少なくありません。
今回は、「一個流し」導入時に現場で直面する心理的・文化的な障壁に焦点を当て、その乗り越え方を具体的に紹介していきます。
「今までのやり方で困っていない」という抵抗
人間は、現状維持を好む生き物です。とくに現場で長く働いている人ほど、「今のやり方でまずまず上手くいっている」と感じており、改善の必要性を感じにくいという特性があります。
このとき、「一個流しにすればこんなに効率的ですよ!」と正論をぶつけても、返ってくるのはたいてい「別に困ってない」「時間がない」「今さらやり方を変えるのは面倒だ」といった反応です。
◆ 対策:問題が“可視化”されない限り、人は変わらない
ここでは、まず「今のやり方がいかにムダを生んでいるか」を定量的・具体的に見せることが有効です。
•例:月次処理の平均完了日数を記録して見える化する
•例:作業完了までに必要なやり取りの回数・人数を集計する
• 例:催促メールの数や対応遅延の件数を数えてみる
目に見える“損失”があって初めて、「変えた方が得だ」と気づくのです。
「まとめた方がラク」という効率幻想
特に事務作業の現場では、「10件まとめて処理すれば、1件ずつやるより手間が減る」という効率幻想が根強く残っています。
確かに、一度テンポに乗って処理できれば楽に感じるかもしれません。しかし、前回までに述べた通り、バッチ処理は手待ち時間・再確認・エラー・調整などの“見えないコスト”を膨らませています。
◆ 対策:部分最適の罠を“体感”で理解してもらう
この思い込みを壊すには、「体験を通じた学習」が有効です。
•簡単なロールプレイやシミュレーション演習(例:1件ずつ vs 10件まとめての比較)
•実際に1日だけ「一個流し」をやってもらい、その後の振り返りで気づきを共有する
•「1件処理するごとに、どこで止まっていたか記録しておく」可視化ワーク
効率幻想を壊すには、“やってみて分かる”しかありません。
組織文化:属人主義と「見えない仕事が偉い」風土
一個流しを進めるには、仕事を「構造化」して他者と共有する必要があります。しかし、属人化が進んだ職場では、「自分だけがわかる仕事」こそが価値であり、自分の存在意義だという暗黙のルールが支配していることがあります。
また、「忙しそうにしている人」や「夜遅くまで残っている人」が評価されるような文化では、仕事を効率的にこなして早く帰る人が逆に肩身の狭い思いをすることすらあります。
◆ 対策:見える仕事を評価し、共有を称賛する制度設計
•「見える仕事」に価値があることを言語化して評価に組み込む
•フローを共有した人、可視化に貢献した人を表彰・感謝する
•チーム内での“仕事の見える化ワーク”を定期的に実施し、情報の共有を仕組みにする
組織文化を変えるには、行動を“褒める”ことが重要です。心理的安全性が確保されることで、改善が進みやすくなります。
「上が変わらないと意味がない」という諦め
一個流しを現場で実践しようとしても、「上司の承認が遅い」「他部署が動いてくれない」など、上流の停滞によってフローが断ち切られることがあります。このとき、「どうせ自分たちが変わってもムダだ」と現場が諦めてしまうケースが多くあります。
◆ 対策:自部署だけでも“完了までの流れ”を作る
•まずは自チーム内だけで完結する仕事を一個流しでやり切る
•その成功体験を、数値・声・変化の形でドキュメント化して“成果報告”
•「流れの詰まり」が上流にあることを可視化し、上司と共有
自部署だけで完了する範囲を極小単位で選び、実行と成果共有を繰り返すことで、周囲を巻き込む力を得ていきます。
まとめ:壁を「壊す」のではなく「溶かす」
「一個流し」は業務改善の技術論ではありますが、実際に導入・浸透させていくには、文化や感情との対話が不可欠です。
•理屈よりも、まずは「気づき」
•気づきよりも、まずは「やってみる」
•やってみるよりも、まずは「共にやる」
こうした段階を踏むことで、「一個流し」は、反発を招く“改革”ではなく、自然としみ込んでいく“進化”へと変わっていきます。
次回(最終回)は、事務作業全体を「流れる構造」として再設計する方法や、部門横断で「一個流し」を定着させるための全体的なアプローチについて紹介します。
全体最適への道筋を明確にする最終回、どうぞご期待ください。
第1回:「一個流し」は製造業だけの話じゃないー事務作業にも効くTPSの原則
第2回:「一個流し」を事務作業に適用するには?ー業務単位の見直しと“流れ”のデザイン
第3回:「一個流し」は調整コストを劇的に減らすー意思決定とチーム連携の加速装置
合同会社タッチコア 代表 小西一有
