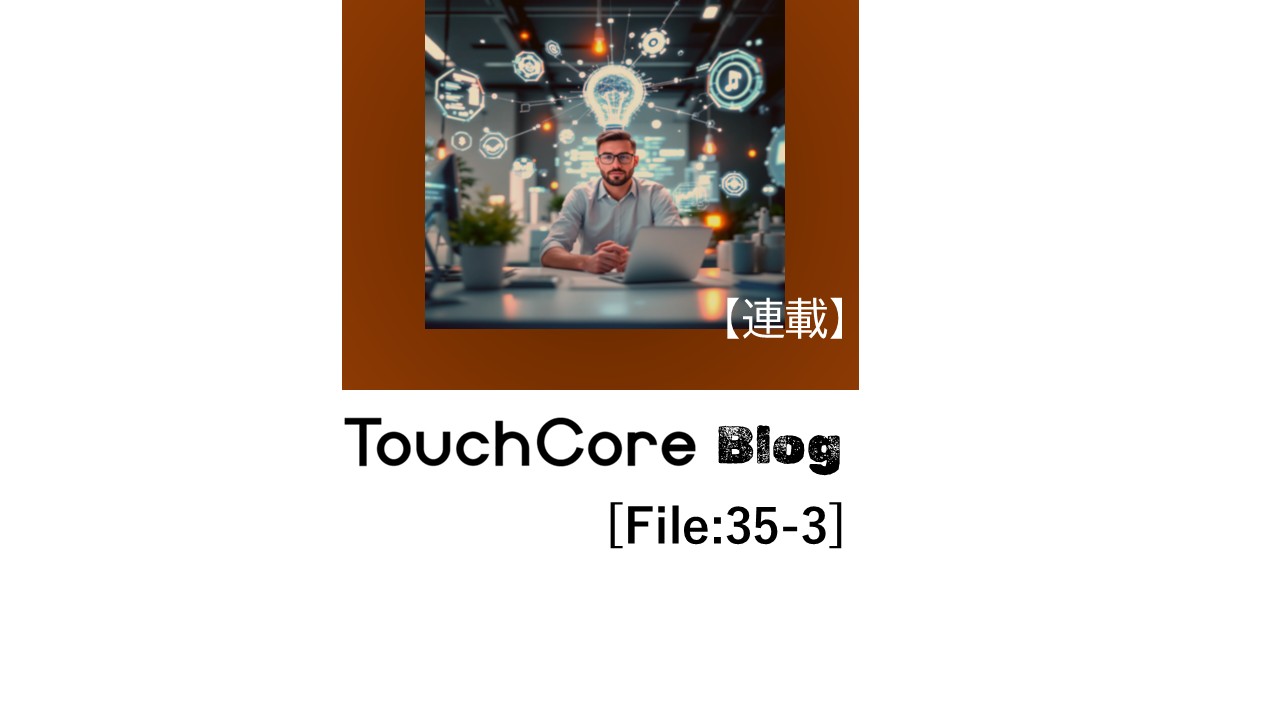
イノベーション創造講座の演習メニューから
前回のBlogでは、イノベーションの源泉は「努力」よりも「発想」であるということ、そして発想を生み出すには“柔らか頭”が不可欠であるという話をお伝えしました。
「柔らか頭」——つまり、固定観念にとらわれず、既存の枠組みの外側へ自由に発想できる思考様式。それは、天性のひらめきや奇抜な感性の持ち主だけのものではありません。誰でも、訓練によって獲得できるスキルなのです。
今回は、イノベーション創造講座で実際に行っている“柔らか頭を育てるための代表的な演習”を3つご紹介します。受講生からの満足度も高く、講座の中核をなすこれらのメニューは、受講後の思考習慣を根本から変える力を持っています。
① ラベリング演習:言葉で「視点」をずらす力
最も基本的で、かつ効果が高い演習が「ラベリング」です。
これは、ある物事に対して「異なる切り口のラベル(=名称)」を与えることで、新たな視点や解釈を生み出すトレーニングです。
たとえば、身近な“電車通勤”という日常を「人間移動の最適化プロセス」とラベリングすれば、そこには新しい問題設定やサービスの可能性が浮かび上がります。
逆に「感情の消耗戦」と捉えれば、メンタルケアやワークライフバランスの観点から再設計の余地が見えてきます。
このように、「意味の言い換え」を繰り返すことで、常識の枠から外れた解釈が可能になり、柔らか頭が育っていきます。
講座では、あらゆるモノ・コトに対して多くのラベルを出す演習を行い、“視点を増やす訓練”を徹底的に行います。
② アイディアカード法:発想のジャンプを促す仕掛け
発想を広げるためには、「一度思考の土台を壊す」ことが必要です。
そのために導入しているのが「アイディアカード」です。
カードには、たとえば以下のような抽象的なラベルが書かれています。
•未来のあたりまえ
•本音が出る瞬間
•不快なのにやめられない
•憧れが止まらない
•なかったことにする技術
これらのカードをランダムに引いて、既存のテーマに強制的に結びつけることで、「そんな切り口、思いつかなかった!」という発想の飛躍を促します。
カードは50枚以上あり、実際の演習では3人1組になって使うことが多く、他者の視点と交わる中でさらなる発想の拡張が起こります。“偶然性”と“対話”が、柔らか頭を刺激するのです。
③ 逆接思考・逆張り発想:常識をひっくり返す訓練
アイディア創出において、「あえて逆を考えてみる」ことは非常に有効です。
講座では「逆接思考」と呼んでいますが、これは一種の“思考のストレッチ”です。
たとえば、
•「便利」→「不便さを楽しむ」
•「効率化」→「あえて非効率を貫く」
•「安全」→「少しの危険が人を動かす」
といった具合に、常識的な前提をいったん反転させてみると、そこに未発見のニーズや課題が見えてくることがあります。
演習では、具体的な社会課題を題材に、「もし○○が××だったら?」という形式で30〜40の逆張り案を出していきます。そしてその中から**“バカげているけれど、なぜか面白い”**アイディアを拾い上げ、企画に昇華させていくのです。
この演習では、思考の深さと軽さを同時に扱うことになるため、非常に盛り上がると同時に、大きな「気づき」が生まれます。
柔らか頭が変えるのは、人生そのものかもしれない
これらの演習を繰り返す中で、多くの受講生が言います。
「自分の見ていた世界が狭かったことに気づいた」
「発想の幅が広がり、仕事に前向きになった」
「人の話を聞く姿勢が変わった」
イノベーションというと、起業や新規事業といった「特別な人の話」のように聞こえるかもしれません。しかし実際には、自分の仕事の進め方を変える力として、また日常の選択を豊かにする視点として、“柔らか頭”は誰にとっても必要なものです。
そして、これは筋トレと同じ。正しい方法で継続すれば、必ず伸びていきます。
「混ざる」ことで生まれる、新しい発想の芽
次回は、この講座の大きな特長である「異業種・異世代の混ざり合い」についてお話しします。多様な価値観が交わることで、なぜ創造性が引き出されるのか? その秘密に迫ります。
合同会社タッチコア 小西一有
||申込み受付スタートしました!||
2025年10月期「イノベーション創造(アイディア創出)講座」
[連載過去回]