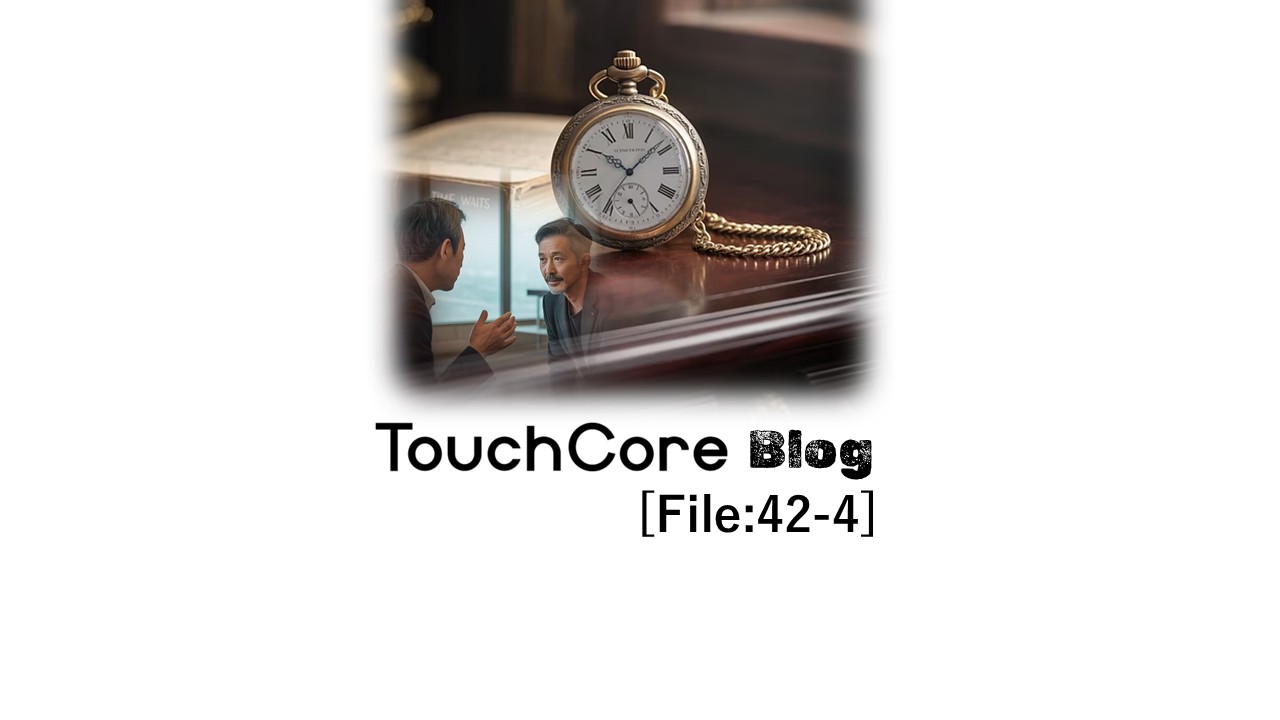
コンサルティングという言葉に付きまとうのは「外部の専門家に任せれば解決策が提示される」というイメージです。報告書やシステム導入といった“成果物”は目に見える形で残りますが、それは時間の経過とともに陳腐化し、いずれ社内に残らなくなります。
一方、アドバイザリーが残すものは「成果物」ではなく「文化」です。つまり、社内に根づく“考える力”そのものです。
成果物よりも「問いの習慣」
アドバイザリーの支援を受けた企業に残る最大の成果は、「問いを立て直す習慣」です。
・そもそもこの業務は本当に必要か?
・この投資は戦略とどうつながっているのか?
・顧客にとっての価値はどこで生まれるのか?
こうした問いを投げかける文化が社内に根づけば、外部のアドバイザーがいなくても企業は自律的に意思決定を行えるようになります。
「伴走型支援」との違い
近年、「伴走支援」という言葉もよく使われます。外部が長期的に寄り添い、課題解決に協力するスタイルです。しかし多くの場合、外部が常にそばにいることが前提になってしまいます。結果、外部依存から抜け出せない状態が続くことも少なくありません。
アドバイザリーはここが決定的に違います。外部が去った後に価値がなくなるのではなく、むしろ外部が去った後にこそ真価を発揮します。短期的な関わりの中で「考える力」を社内に根づかせ、企業が自走できる状態を残すことを目的としているからです。
実例:問いの文化が残った企業
ある企業では、システム刷新のために当社に相談がありました。当初は「要件定義書を書いてほしい」という依頼でしたが、私たちはあえて「そもそも刷新の目的は何か?」という問いから始めました。
議論を重ねるうちに、刷新よりも業務フローの再設計の方が本質的課題であることが判明。結果、システム投資は半減し、余剰資金を新規事業に振り向ける決断ができました。数年後、同社の幹部に再会したとき、彼はこう話してくれました。
「意思決定の場では、まず問いを立て直すことから始めるようになりました」
これは「報告書」や「システム」ではなく、「問いの文化」が社内に残った証拠です。
成果物より「文化」を残すという発想
アドバイザリーの本質は、知識や資料を提供することではなく、考え方を残すことにあります。
・問いを立て直す習慣
・構造を見抜く視点
・意思決定の自律性
これらは外部がいなくなっても生き続け、経営を支える資産となります。
成果物は消耗品ですが、文化は企業の血肉となり、持続的に組織を成長させるのです。
皆さんへ
あなたの会社に残っているのは「報告書」でしょうか、それとも「考える文化」でしょうか。
外部がいなくなった途端に意思決定が止まってしまうのでは、本当の変革とは言えません。
本当に必要なのは「一時的な答え」ではなく「考え続ける力」。アドバイザリーは、その力を社内に根づかせるために存在しているのです。
明日(第5回)は、「戦略的アドバイザリーが拓く未来」と題し、これまでの総括と日本企業にとっての意義を展望します。
合同会社タッチコア 小西一有
第1回:なぜ「コンサルティング」ではなく「アドバイザリー」なのか
第2回:経営における「情報」の特性とアドバイザーの役割
第3回:アドバイザーに必要な資質とは何か