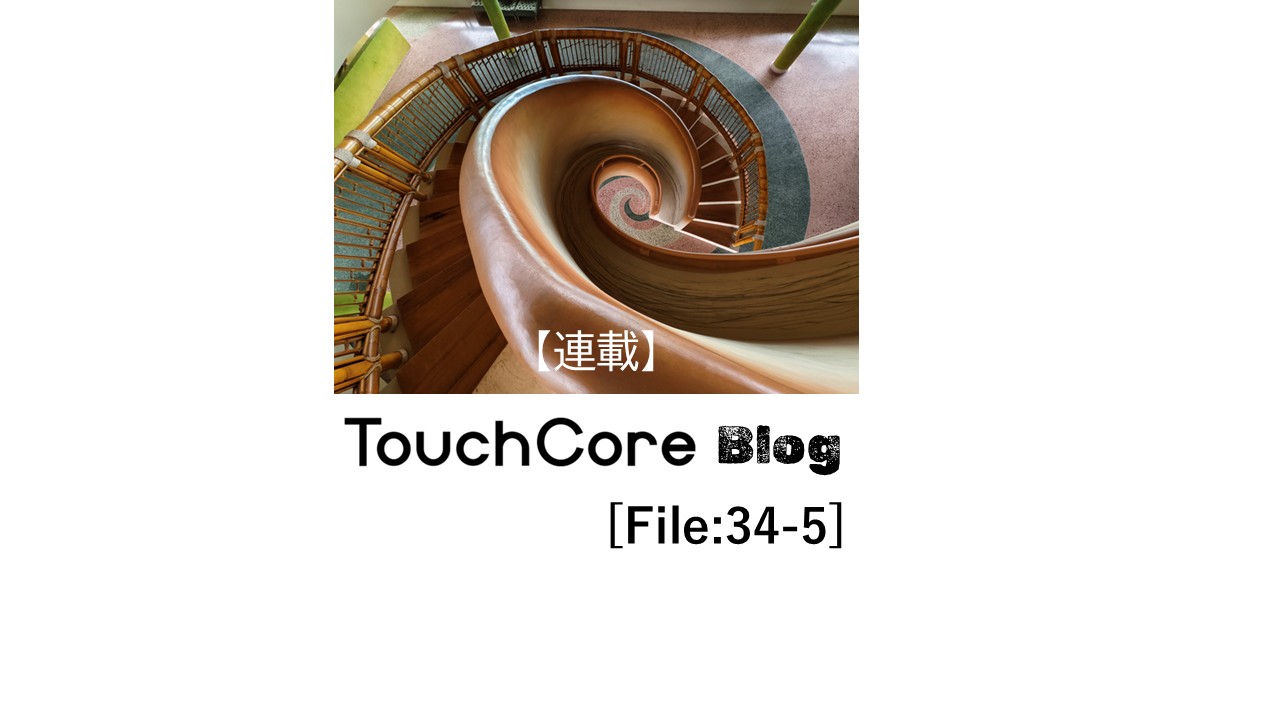
はじめに:個人の改善から組織の変革へ
これまでの4回では、「一個流し」というシンプルな考え方が、事務作業のリードタイム短縮、調整コスト削減、可視化と属人化の解消、そして判断品質の向上に大きな効果をもたらすことを見てきました。
しかし、一個人や一部門だけが改善しても、全体の仕事がスムーズに流れるとは限りません。最終回となる今回は、「一個流し」を組織全体で定着させるために必要な視点とアプローチについて、業務構造設計の観点から掘り下げていきます。
「業務は流れである」という視点を持つ
多くの組織では、仕事を「担当者ごとのタスク」として切り出して管理しています。しかし、重要なのは “どのように受け取り、どのように次へ渡すか”という流れの設計です。
一個流しの本質とは、「処理そのもの」ではなく、「流れを滞らせない構造」にあります。つまり、仕事を川のように流れるものとして再設計する必要があります。
◆ 業務構造設計の基本原則
1.起点と終点を明確にする:誰が何をトリガーに仕事を開始し、何をもって完了とするか
2.手渡しポイントを見える化する:次工程が誰なのか、いつ、どの形式で渡すかを明文化
3.滞留しない仕掛けをつくる:引き継ぎルール、期限、代替ルートなどの整備
「部門横断の流れ」を可視化する
一個流しは、自部署の中で完結する作業だけではなく、部門間をまたぐプロセスにおいてこそ真価を発揮します。
たとえば以下のような「分断されがちなプロセス」こそ、流れを設計し直す余地があります。
•営業 → 見積 → 契約 → 請求 → 入金
•人事 → 入社対応 → IT準備 → 勤怠管理 → 給与計算
•顧客問合せ → ヘルプデスク → 開発部門対応 → フィードバック
これらはどこか一箇所でも滞ると、全体がストップします。
◆ 部門横断での「一個流し」実現のステップ
1.現状の業務フローをプロセスマップとして可視化する
2.各部門にとっての「出口」と「入口」の曖昧さを洗い出す
3.「流れを止めないためのルール・役割分担」を合意形成する
4.改善後も定期的なふりかえりとメンテナンスを行う
重要なのは、「上流工程の乱れは下流に影響を与える」ことを全員が理解し、部門間での“責任の手渡し”をきちんと設計することです。
「流すことが正義」という価値観を根付かせる
一個流しを全社的に浸透させるには、単なる改善活動ではなく、組織文化として定着させる必要があります。
そのためには、以下のような価値観と制度設計が重要です。
◆ 「流すことを褒める」文化
•案件が早く完了したチームを称賛する
•手待ちを解消する工夫を表彰する
•属人化の解除やプロセス可視化に取り組んだメンバーを評価する
◆ KPI設計に“流れ”の指標を入れる
•リードタイム(着手から完了までの平均時間)
•スループット(1日あたりの処理完了件数)
•滞留率(未処理案件数の割合)
•処理バラつき(部署間の完了スピードの差)
これにより、“成果物”ではなく“流れ”に注目が集まり、行動様式が変わっていきます。
「ツールやシステム導入も「流れの補助」として設計する
一個流しを現場で実践しようとしても、「上司の承認が遅い」「他部署が動いてくれない」など、上流の近年は多くの企業で、SaaS型のワークフローシステムやプロジェクト管理ツールを導入しています。しかし、「ツールを導入したのに業務が変わらない」というケースが後を絶ちません。
その理由は、業務の“流れ”そのものを再設計せずに、現状のやり方をシステムに置き換えているからです。
◆ IT導入時の注意点
•フローの再設計を伴わないツール導入は“単なるデジタル化”に終わる
•「次に誰が何をやるか」が見える仕組みになっているかをチェックする
•承認ルート・期限・通知の設計が“滞り解消”に貢献しているかを検証する
「一個流し」の思想は、IT化の骨格を形作る設計思想として非常に強力です。
まとめ:一個流しは“改善活動”ではなく“設計思想”である
ここまで5回にわたって、「一個流し」の本質とその事務作業・業務構造への適用方法をお伝えしてきました。
最終的にお伝えしたいのは、「一個流し」は単なる効率化手法ではなく、“業務の構造をどう設計するか”という思想の問題であるということです。
•滞留しないように、最初から流れを作る
•エラーが出る前提で、早期に発見できる構造にする
•人が判断せずとも、次に進む設計をつくる
このような“流れる業務構造”を志向することで、個人の改善が、チームの連携へ、そして組織の全体最適へとつながっていきます。
終わりに:
TPSのエッセンスである「一個流し」は、決して製造業に閉じた手法ではありません。
むしろ、仕事の流れが見えにくく、属人化とバッチ処理に覆われがちな事務作業の世界こそ、最大の適用対象です。
本連載が、皆さんの職場における“業務の再設計”のヒントになれば幸いです。
職場の仕事の「流れ」に滞りがあるのでは…など違和感が改善の第一歩です、お気軽にご相談ください。無料相談のお申込みはこちら
第1回:「一個流し」は製造業だけの話じゃないー事務作業にも効くTPSの原則
第2回:「一個流し」を事務作業に適用するには?ー業務単位の見直しと“流れ”のデザイン
第3回:「一個流し」は調整コストを劇的に減らすー意思決定とチーム連携の加速装置
第4回:「一個流し」の導入を阻む“見えない壁” ーなぜ変われないのか、どう変えていくのか
合同会社タッチコア 代表 小西一有
