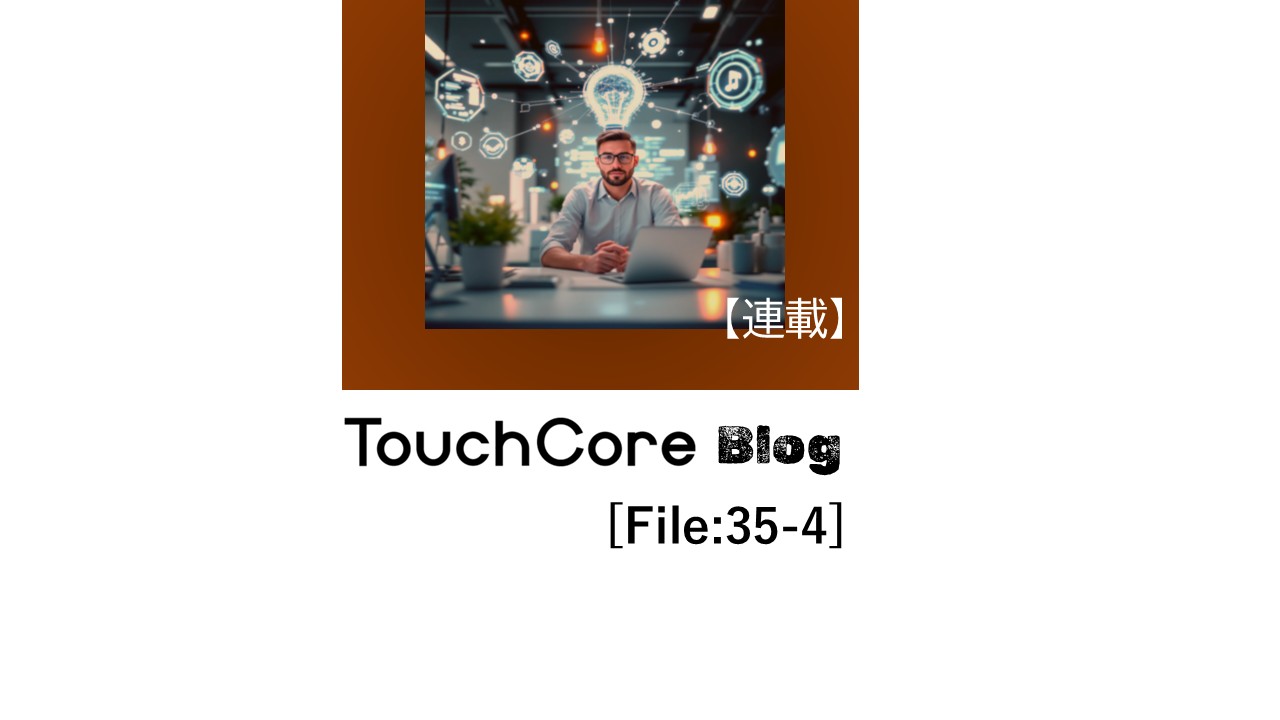
イノベーションは、異質が出会うところに宿る
イノベーションの源泉は、ひとりの天才によるひらめきだけではありません。
むしろ私たちの現実において、創造的なアイディアが生まれる瞬間とは、「異なる何か」が出会い、交差したときにこそ起こります。
•異なる業種
•異なる立場
•異なる価値観
•異なる年代
こうした“異質”のもの同士が混ざり合うことで、それぞれが持つ視点の枠が揺さぶられ、新しい視点、新しい問い、新しい関係性が立ち上がってくるのです。
本日は、この「混ざることの力」について、そしてイノベーション創造講座がなぜ「異業種・異世代・異役職」の混成で設計されているのか、その背景をお話しします。
同じ会社・同じ部門では、似たアイディアしか出てこない
多くの企業では、創造的なアイディアを生むために社内ワークショップやアイディアソンを開催しています。
しかし、参加者が同じ部門、同じ価値観、同じ業務文脈に縛られていると、どんなに頑張っても、出てくるアイディアは「すでにどこかで聞いたことのあるもの」に落ち着いてしまいがちです。
なぜか?
それは、共通言語が多すぎると、対話がスムーズになりすぎるからです。
共通言語とは便利なようでいて、裏を返せば“問い直す必要のない前提”であり、思考の幅を狭めてしまう側面もあります。
逆に、立場や文化が異なる人と対話する場では、「えっ、それどういう意味ですか?」という問いが頻出します。
この“わからなさ”こそが、発想のブレークスルーを生む起点になります。
イノベーション創造講座では、意図的に「異なる業種・異なる年齢層・異なる役職」の方々が交わるように設計しており、この違和感と対話の繰り返しによって、参加者一人ひとりの思考の型が崩され、新たな視点が芽生えていきます。
フレッシュさ vs 経験値─意外にも輝くのは?
講座に関心を寄せてくださる組織の方から、よくこう尋ねられます。
「この講座って、若手向きなのですよね?」
たしかに、「柔らか頭」「アイディア創出」と聞くと、若くて柔軟な人たちこそ向いているように感じるかもしれません。
もちろん若手の方にも非常に効果の高い講座です。しかし、私の経験上、本当に面白いアイディアを出してくるのは、むしろ部課長クラスの管理職なのです。
若手が遠慮して出せないような“本気の逆張り”や、“大人の余裕ある視点”が、場をぐっと活性化させます。そして何より、「もう自分をよく見せようなんて思っていない」という境地に達した管理職の発想は、吹っ切れていて自由なのです。
そして私は、こうした管理職こそが、若手が自由に、のびのびと発想できる環境を整える責任者であってほしいと願っています。
「お前の考え、ちょっと面白いじゃないか」と背中を押す一言。
「自由にやってみろ」と言ってあげる余裕。
それがあるかどうかで、組織の発想力は天と地ほど変わるのです。
「違い」はぶつけ合うものではなく、溶け合わせるもの
異質なものが集まる場は、最初はややぎこちないものです。
遠慮もあるし、理解できない言葉も飛び交います。
でも、そこで大事なのは「相手を説得する」のではなく、「一緒に考えてみる」という姿勢です。
•営業とエンジニア
•公務員と起業家
•20代と50代
•管理職と若手
こうした人々が共に一つの課題に向かうとき、アイディアの「化学反応」が生まれます。
しかも、そこから生まれるのは、誰かひとりの手柄ではない。チーム全体で共有できる創造性です。
イノベーション創造講座では、そうした“溶け合わせ”のデザインに徹底してこだわっています。
混ざる体験は、視野と可能性を拡張する
講座が終盤に差し掛かる頃、参加者の多くがこんな感想を漏らします。
•「自分にはなかった発想を、人の口から聞いて驚いた」
•「普段交わらない立場の人と対話するだけで、こんなに刺激があるとは」
•「社内ではもう少し、違いを受け入れる姿勢を持ちたいと思った」
混ざることは、視野を広げ、言語を増やし、可能性の幅をぐんと拡張してくれます。
そして、それは必ず組織にも還元されていきます。
組織が生まれ変わるためには、まず個人が多様性を経験し、自らの“見方”を更新することが必要なのです。
アイディアは「ビジネス化」しなくてもいい?
次回(最終回)では、講座の設計思想のひとつである「アイディアは必ずしもビジネス化を前提としない」という考えについて掘り下げます。実現性よりも“発想そのもの”に意味があるというのは、どういうことでしょうか?
合同会社タッチコア 小西一有
||申込み受付スタートしました!||
2025年10月期「イノベーション創造(アイディア創出)講座」
[連載過去回]